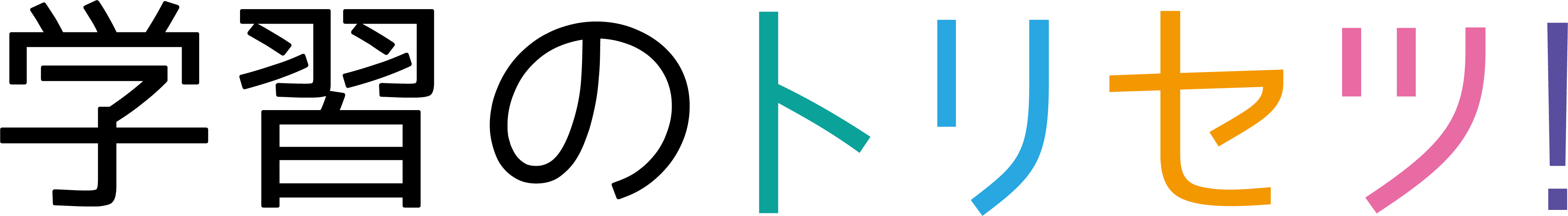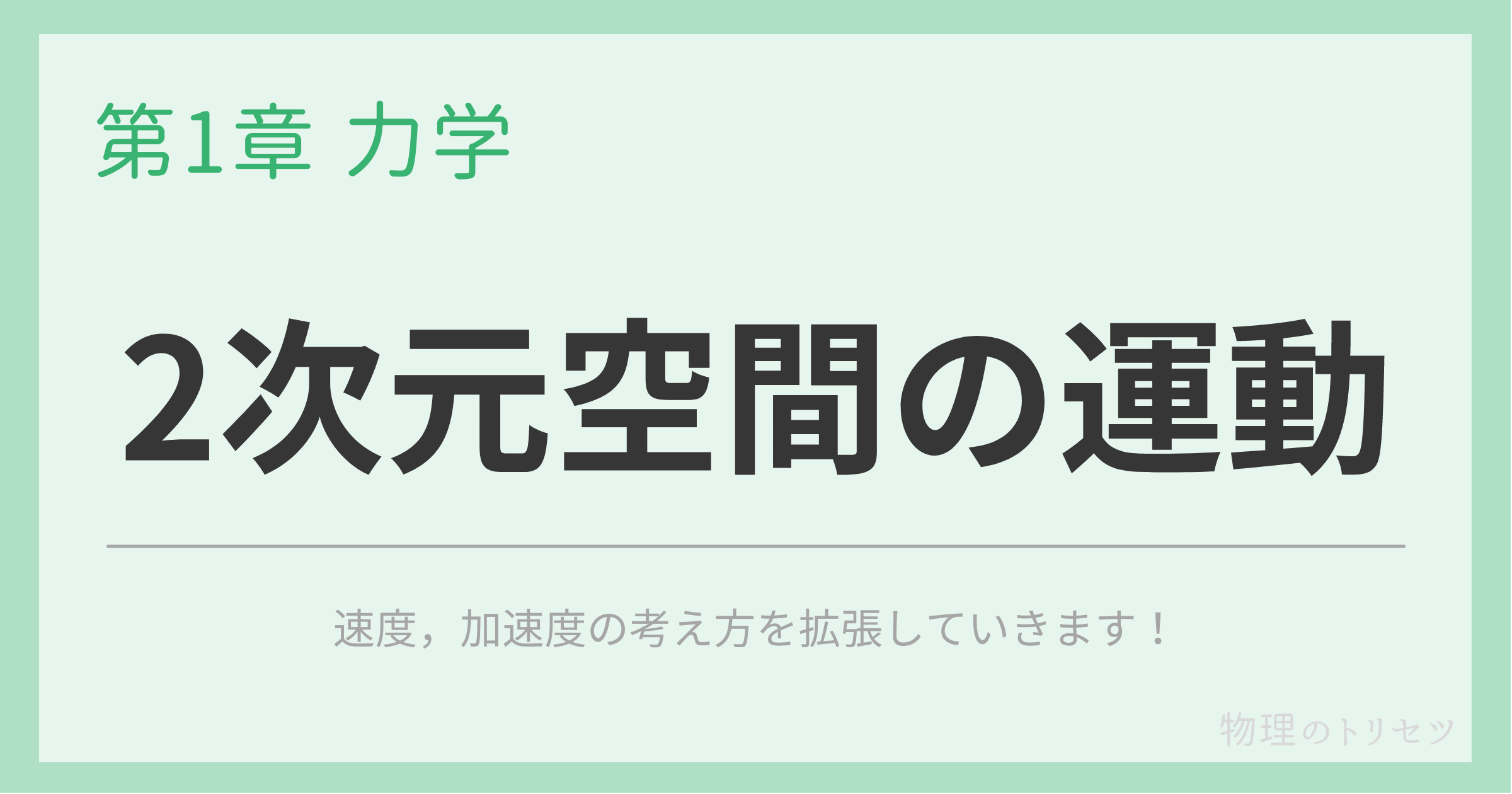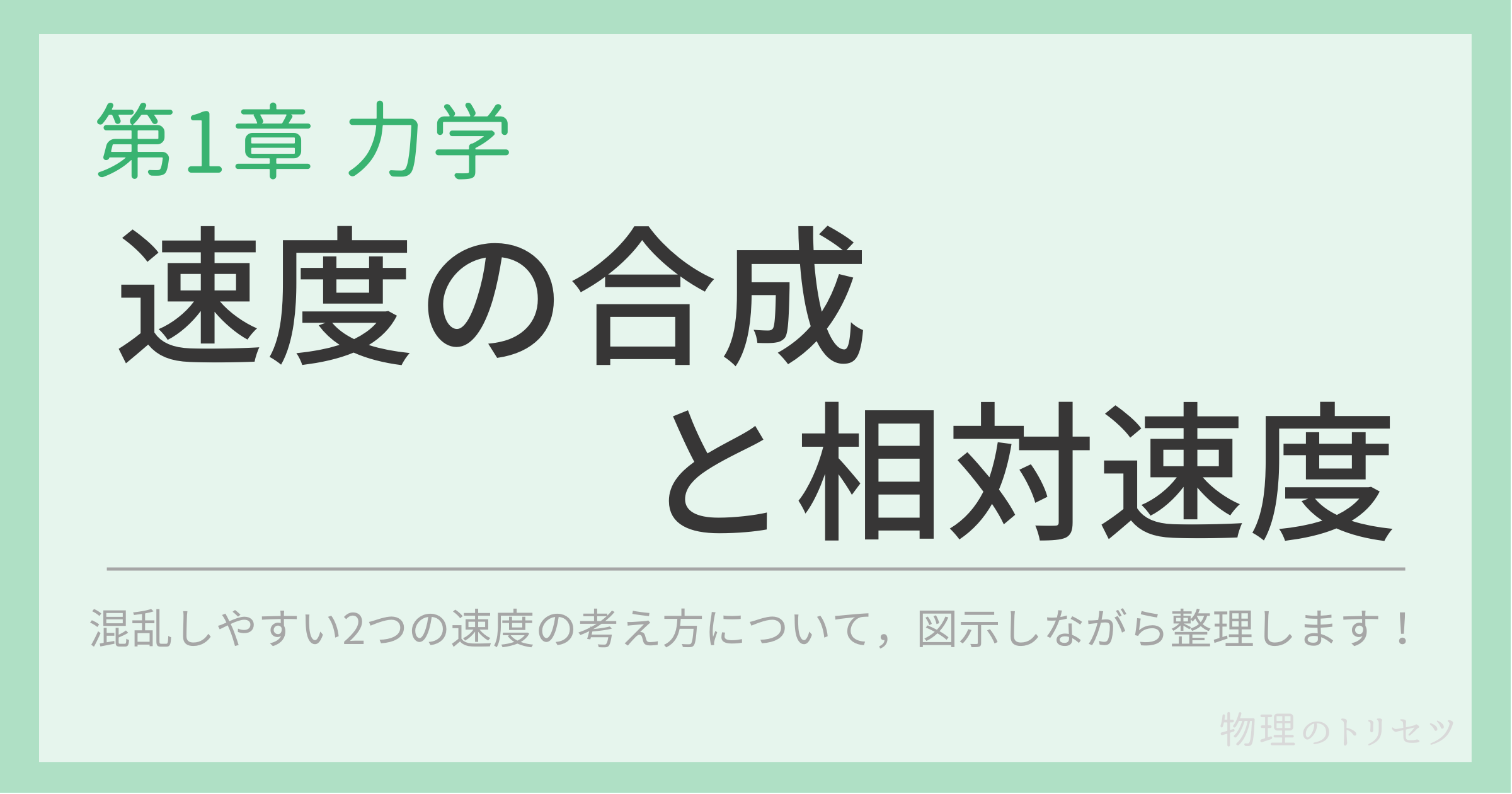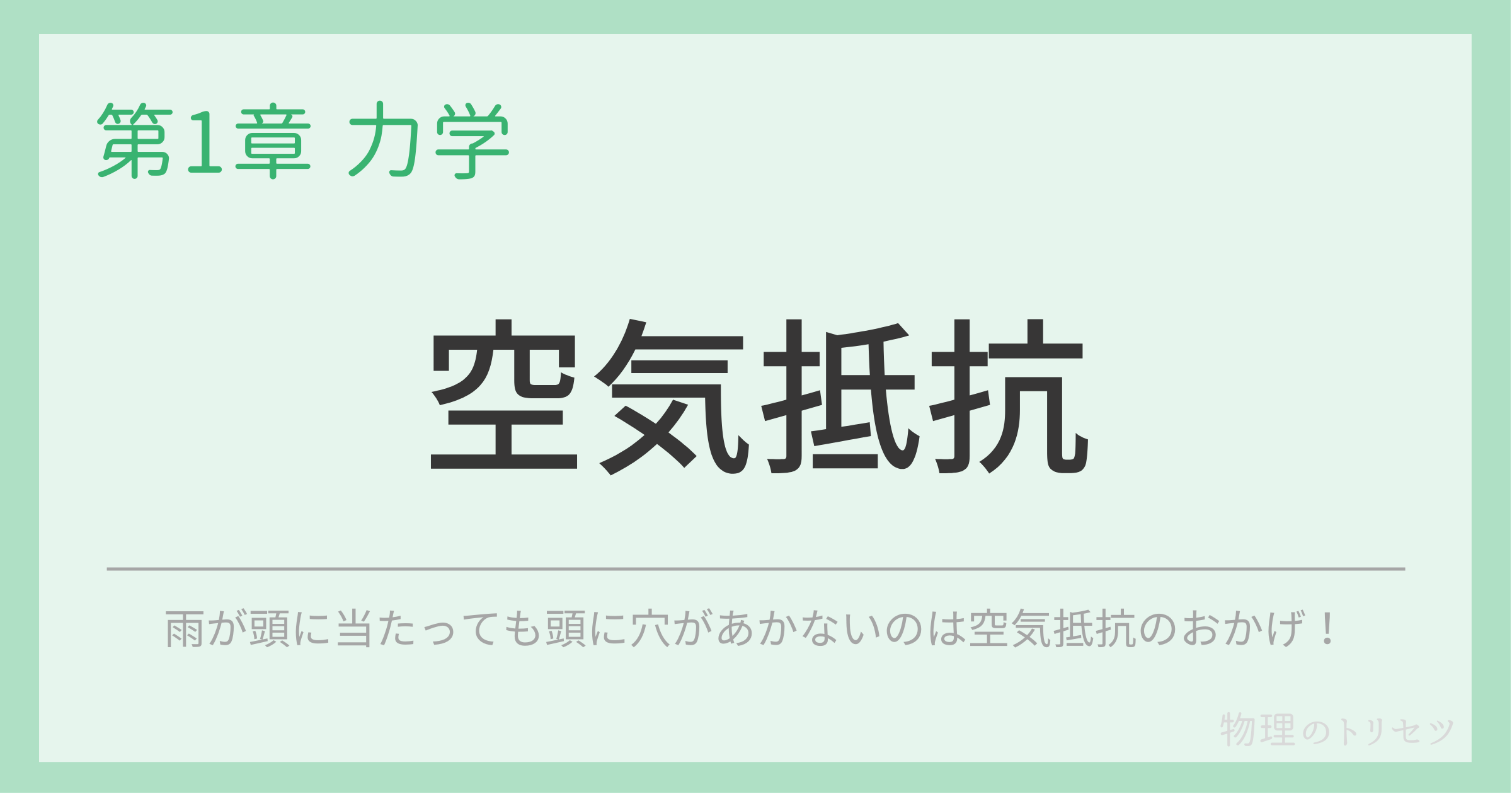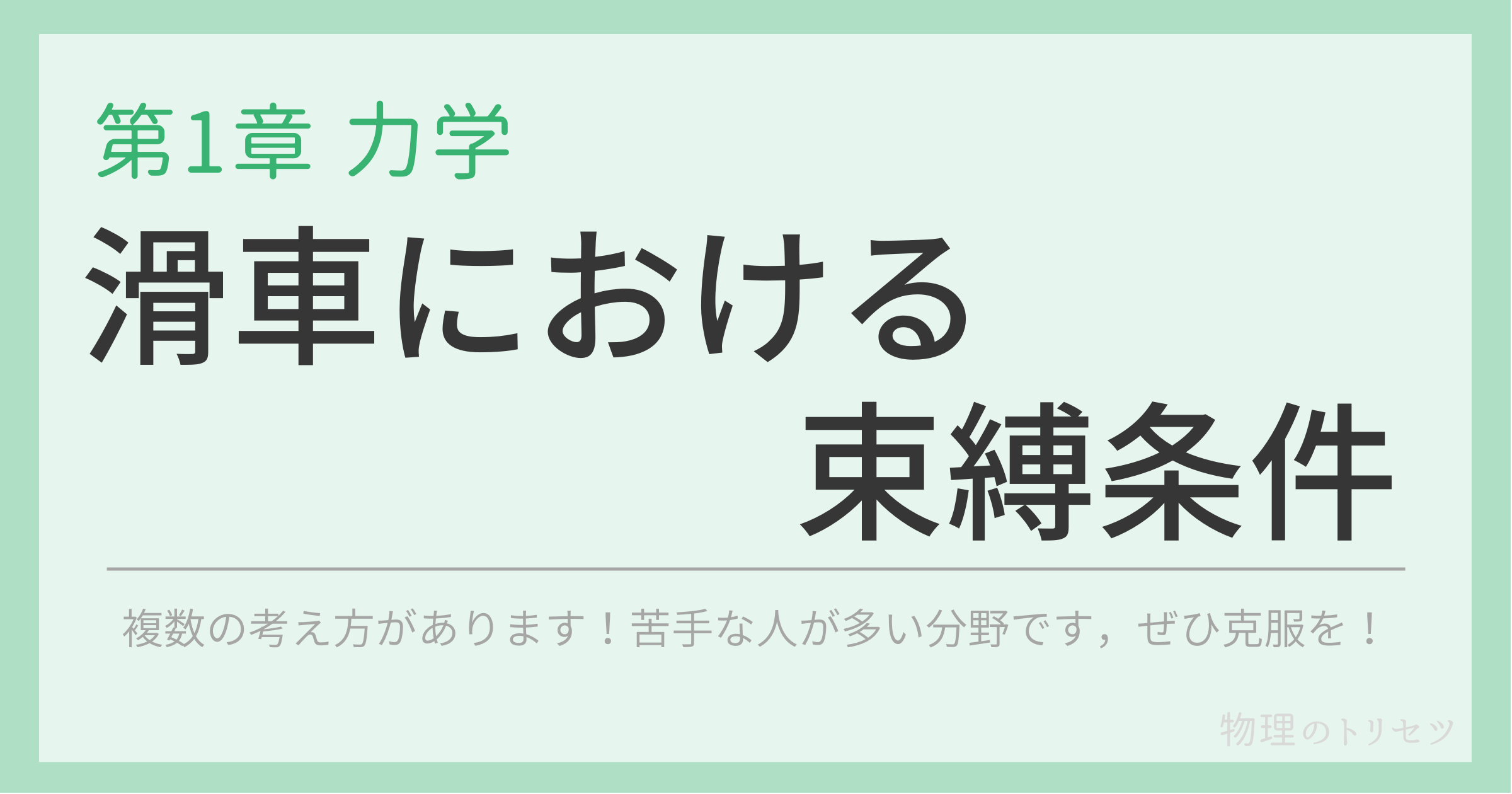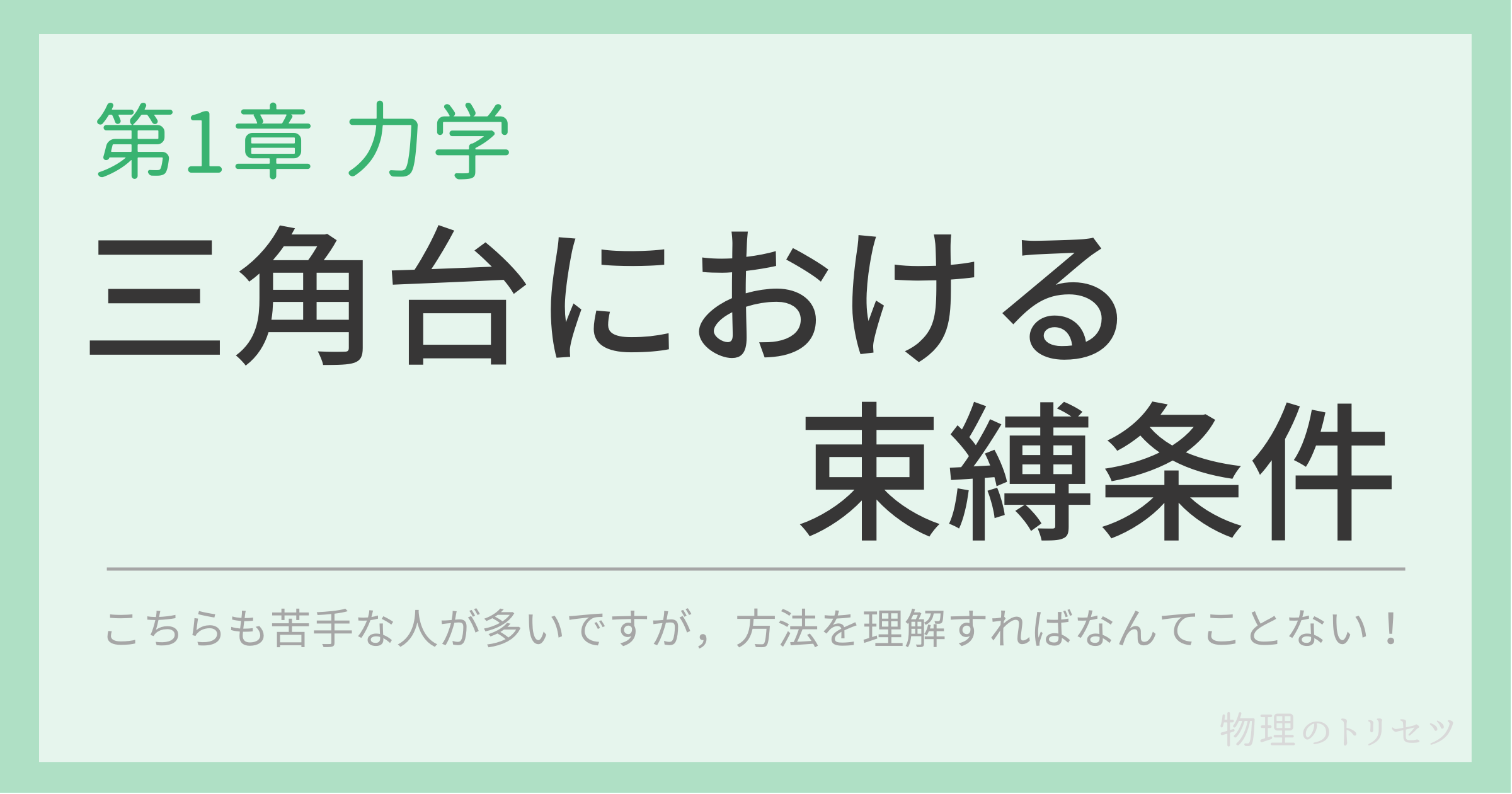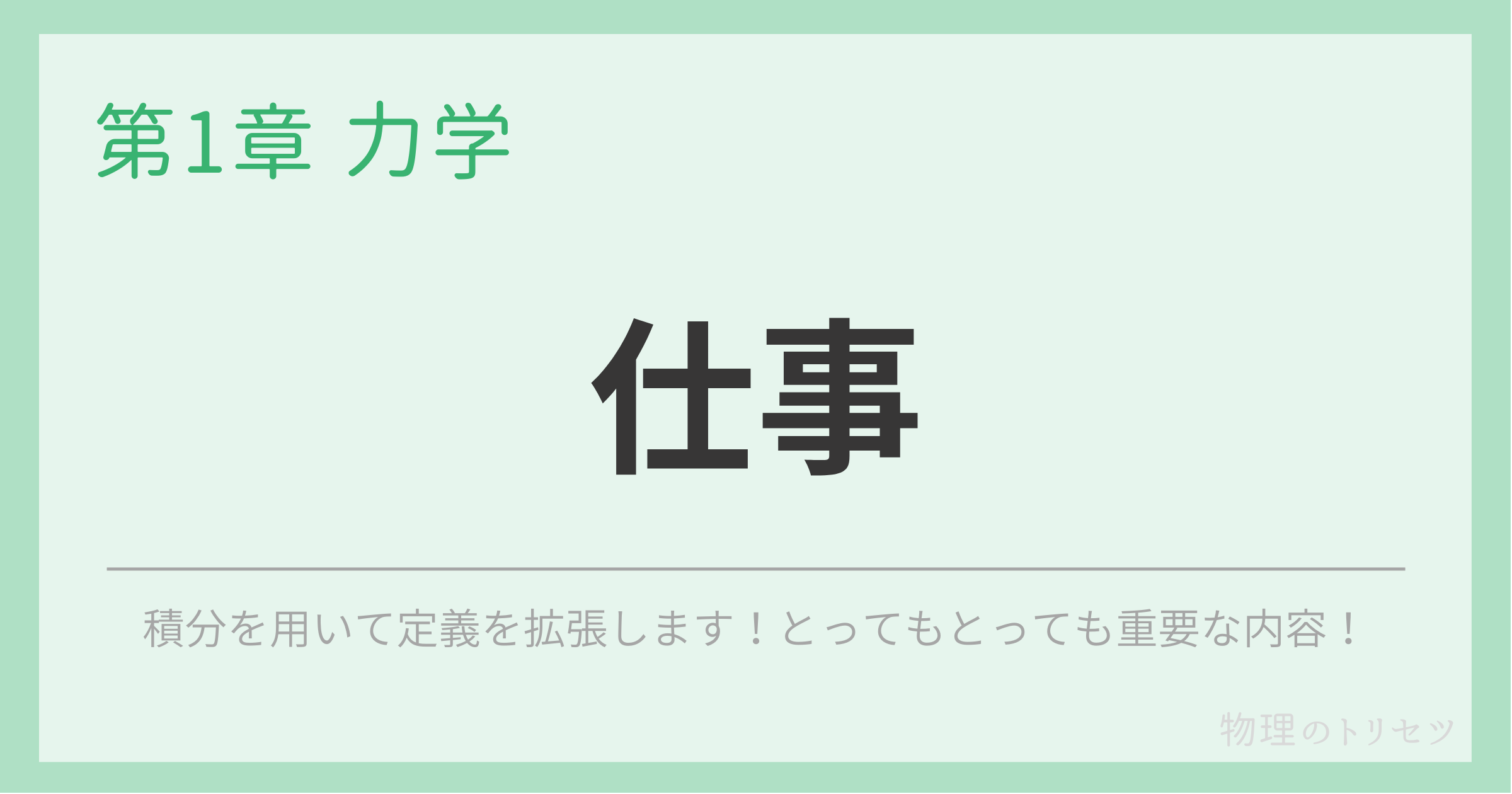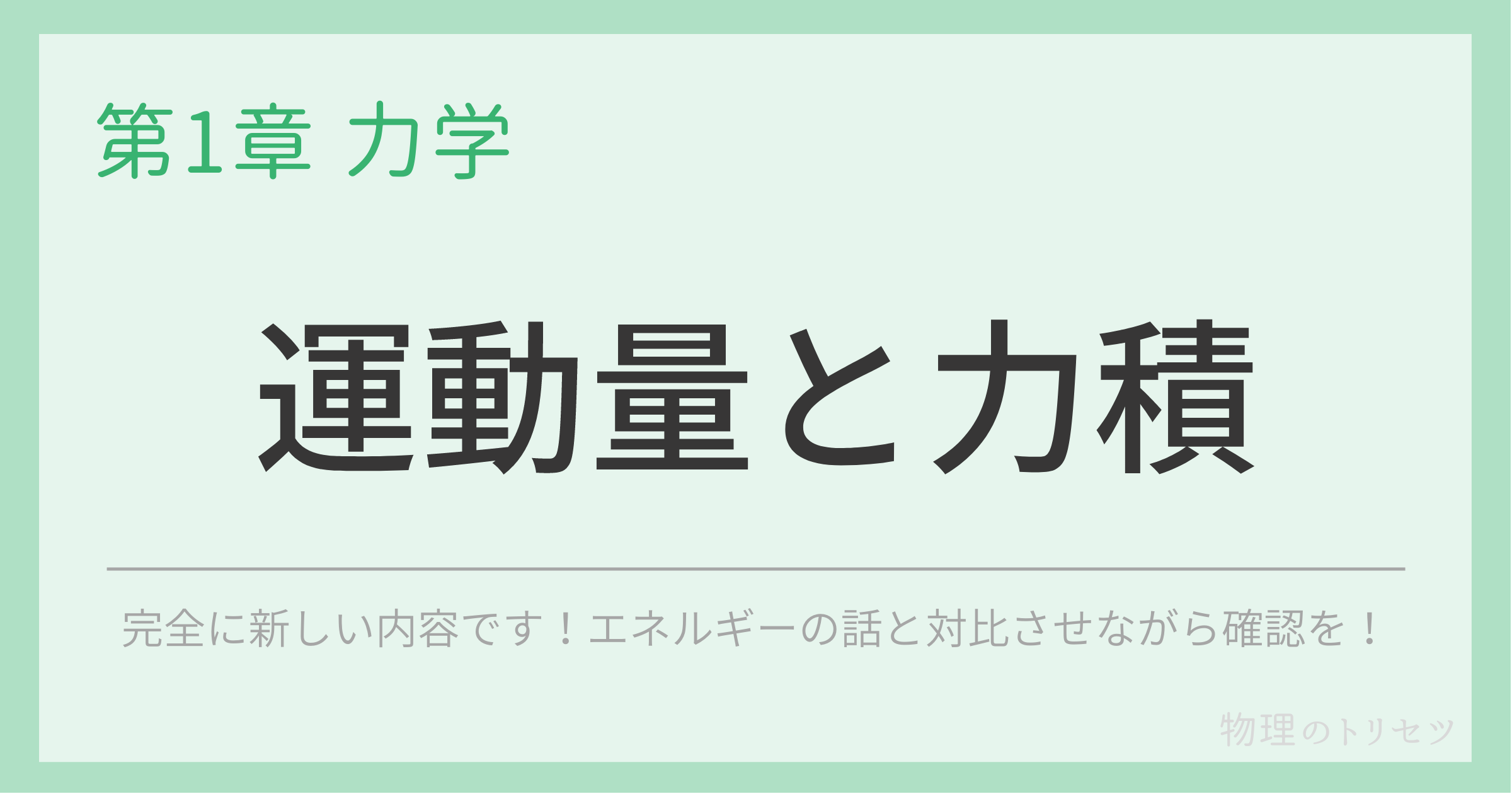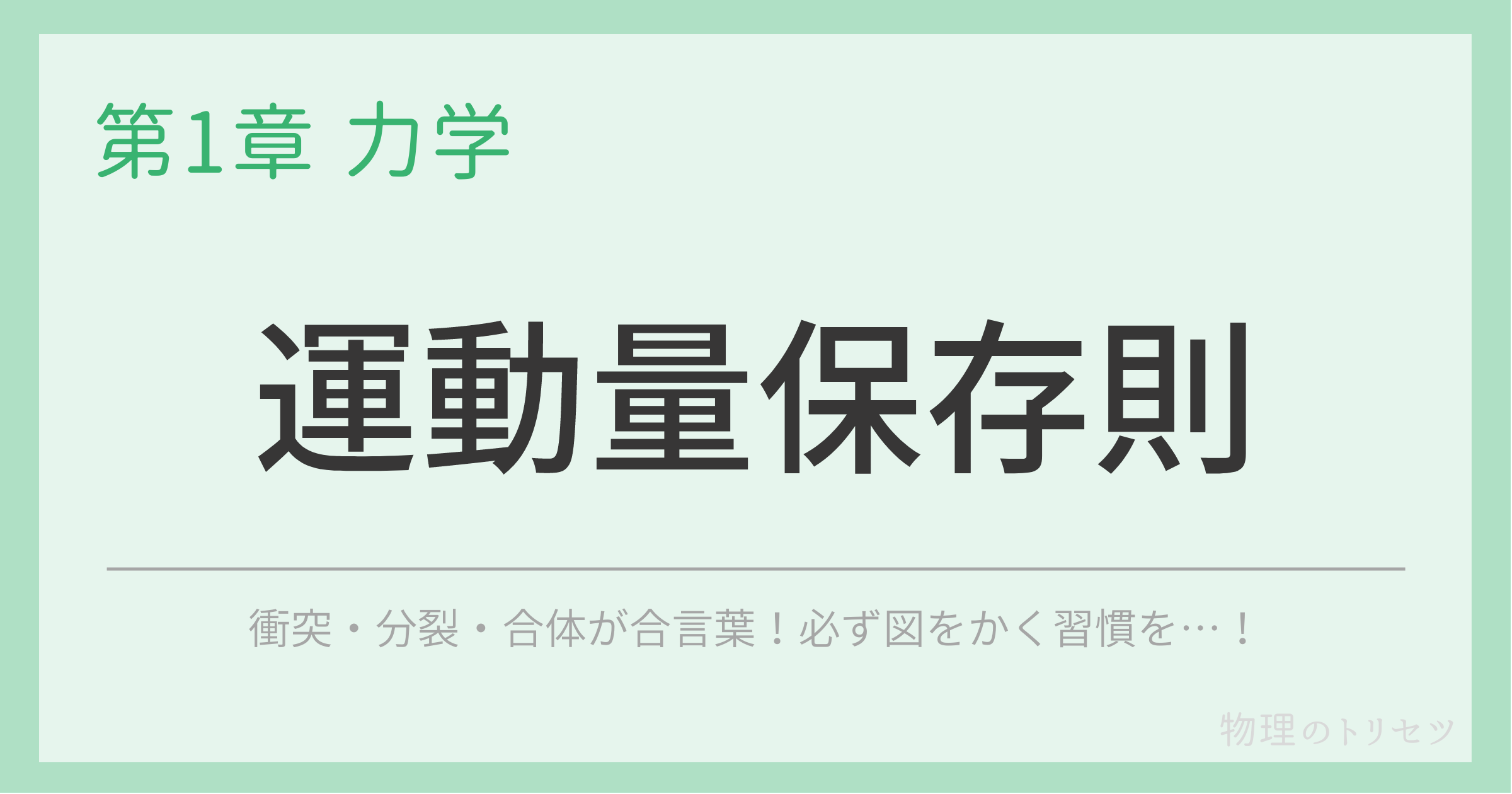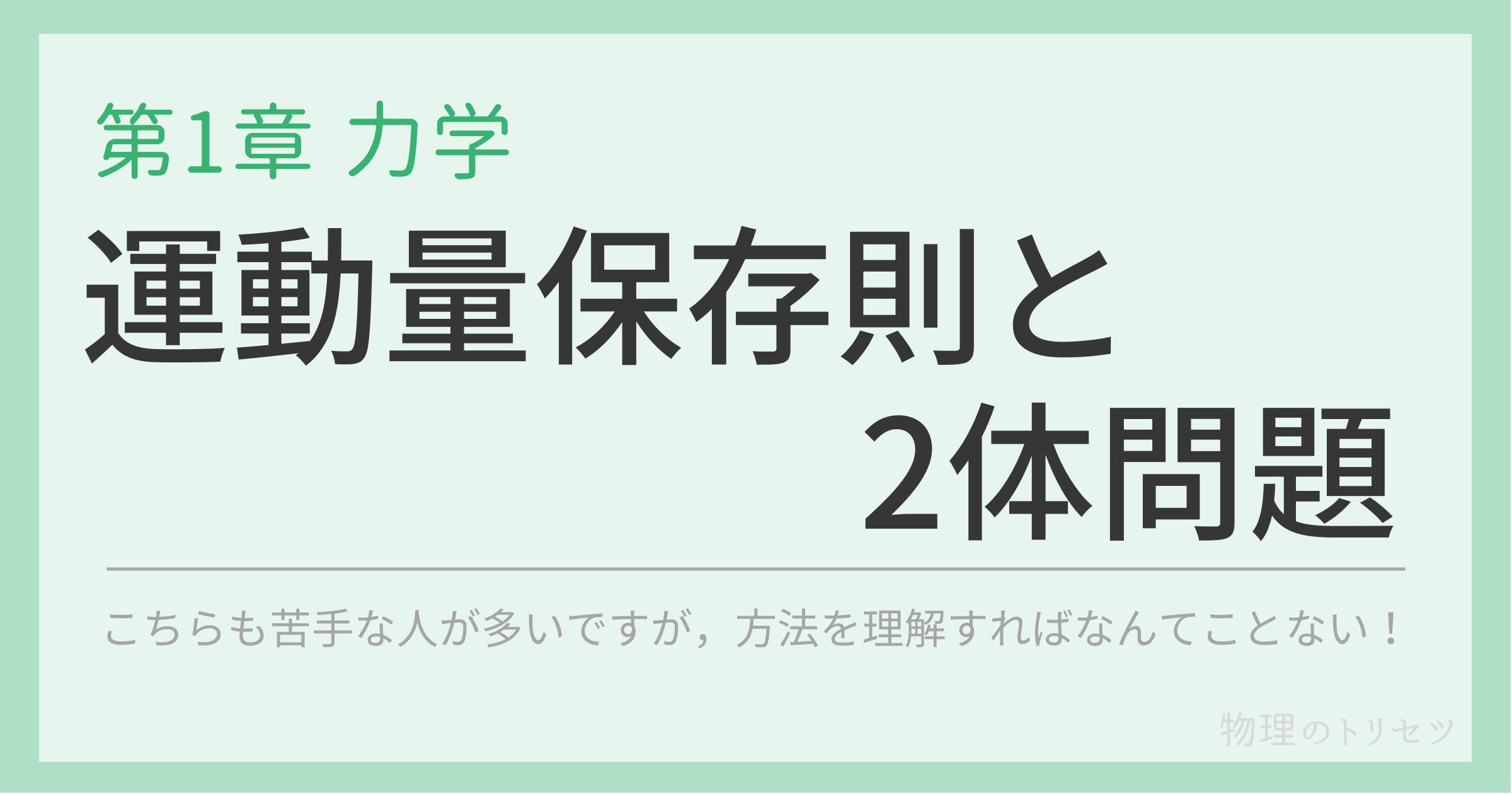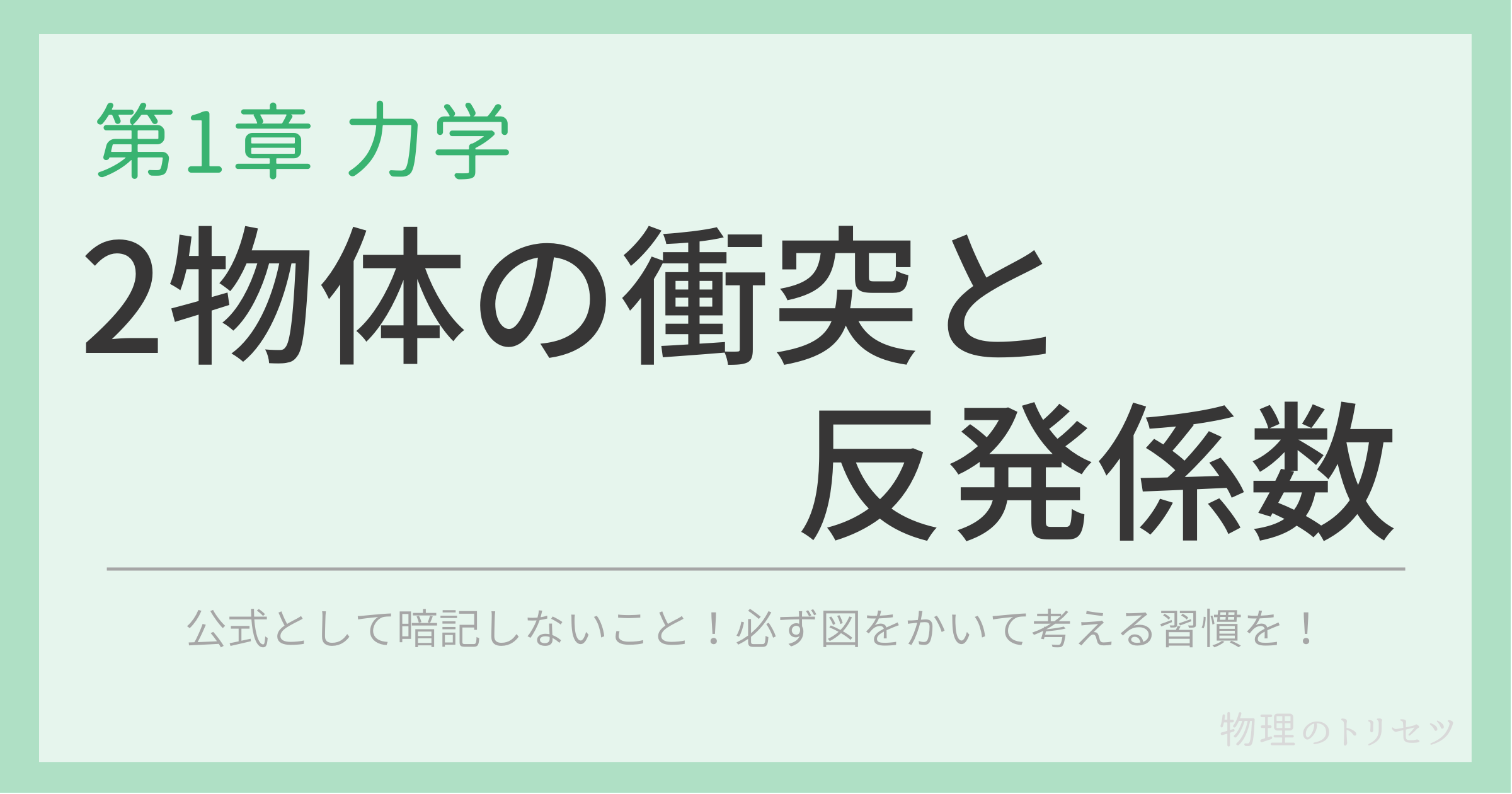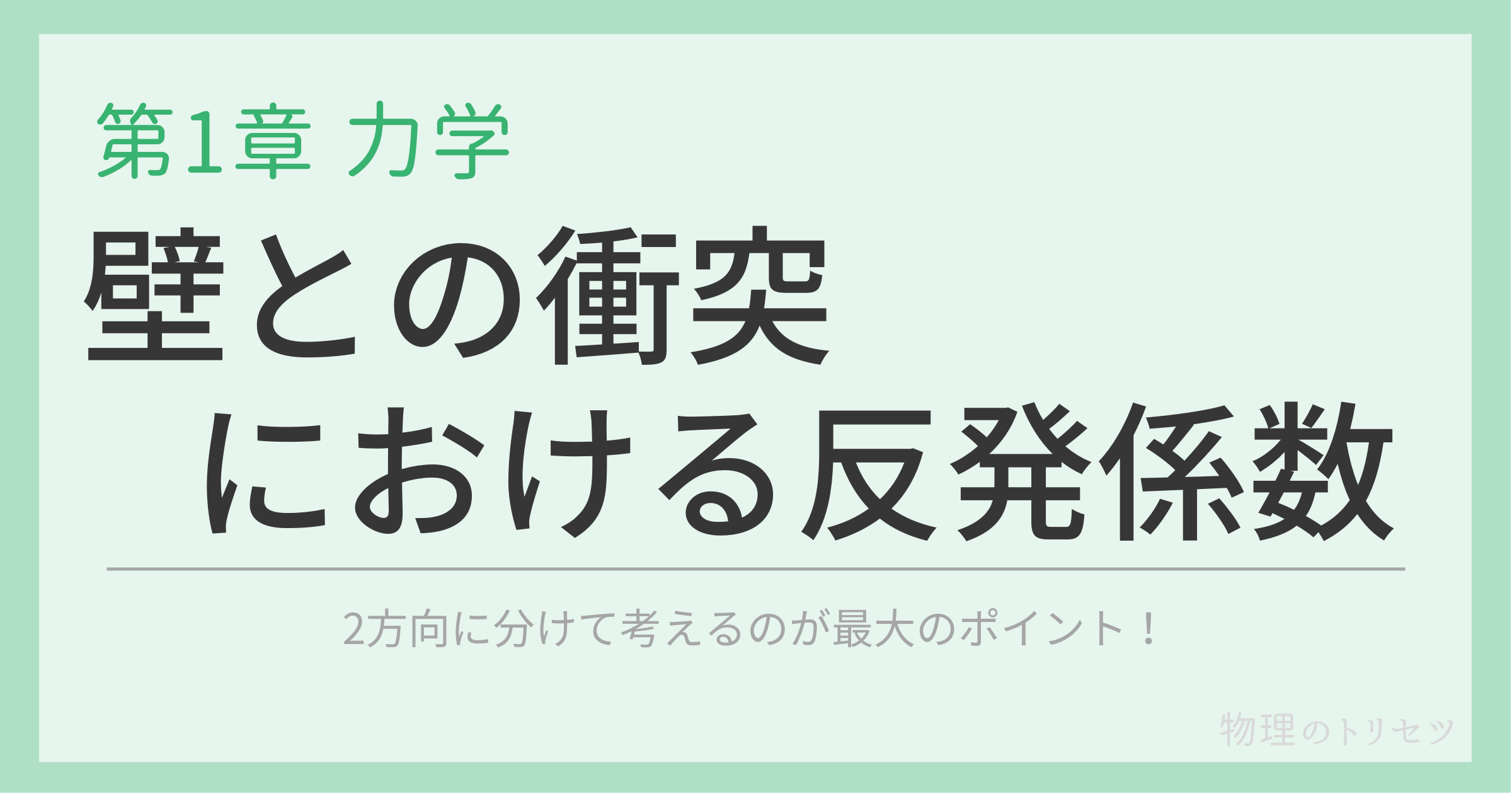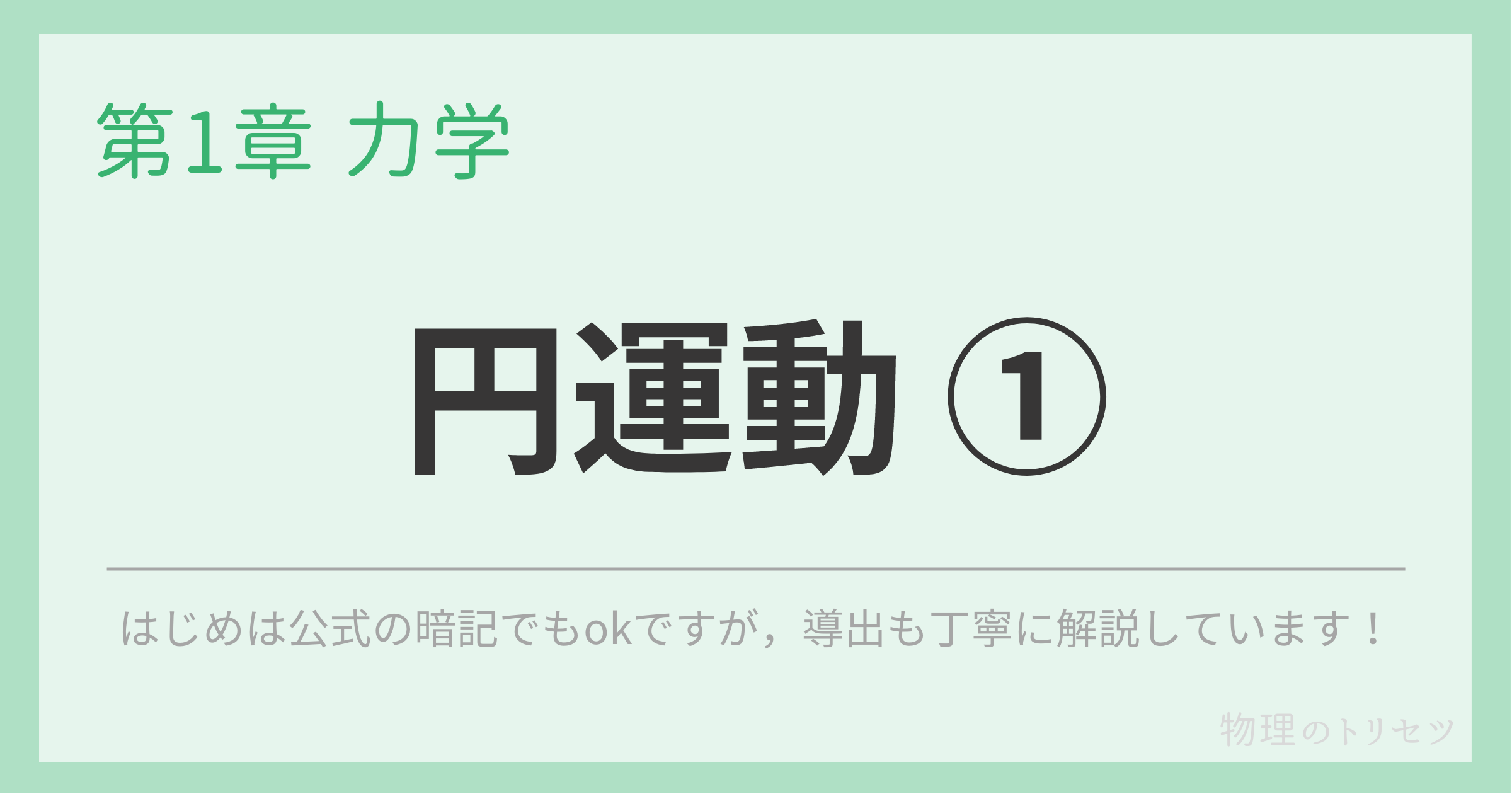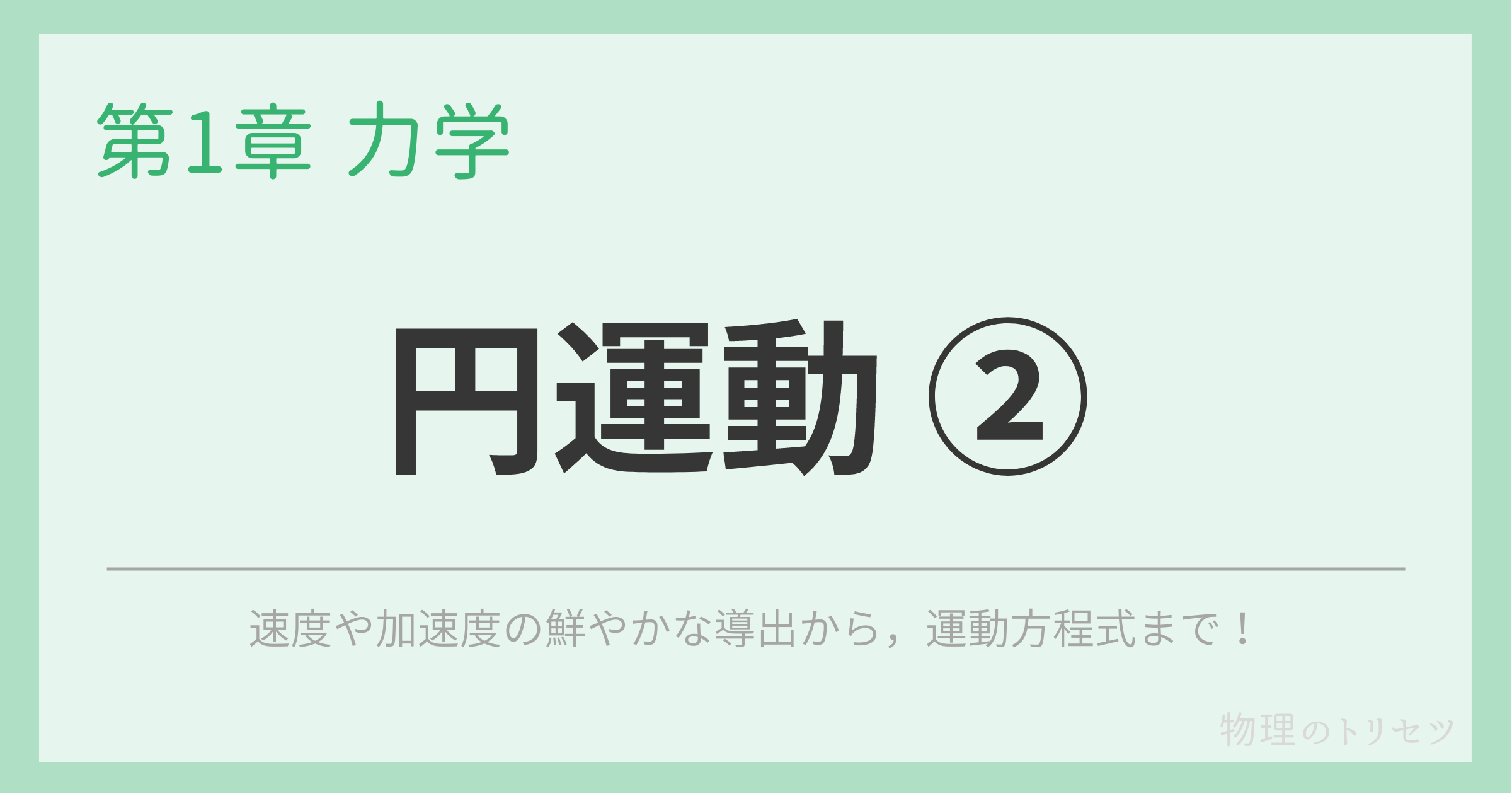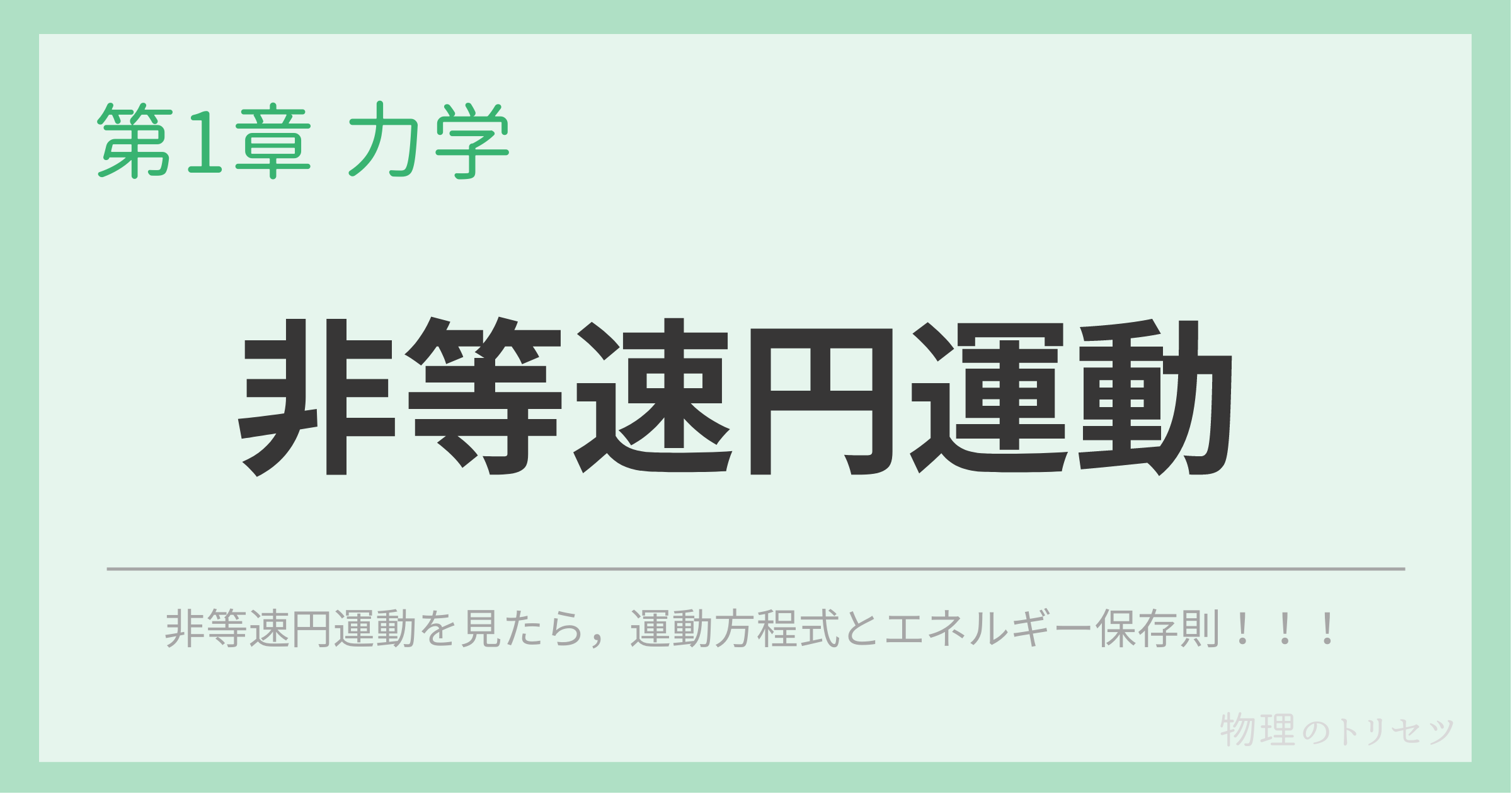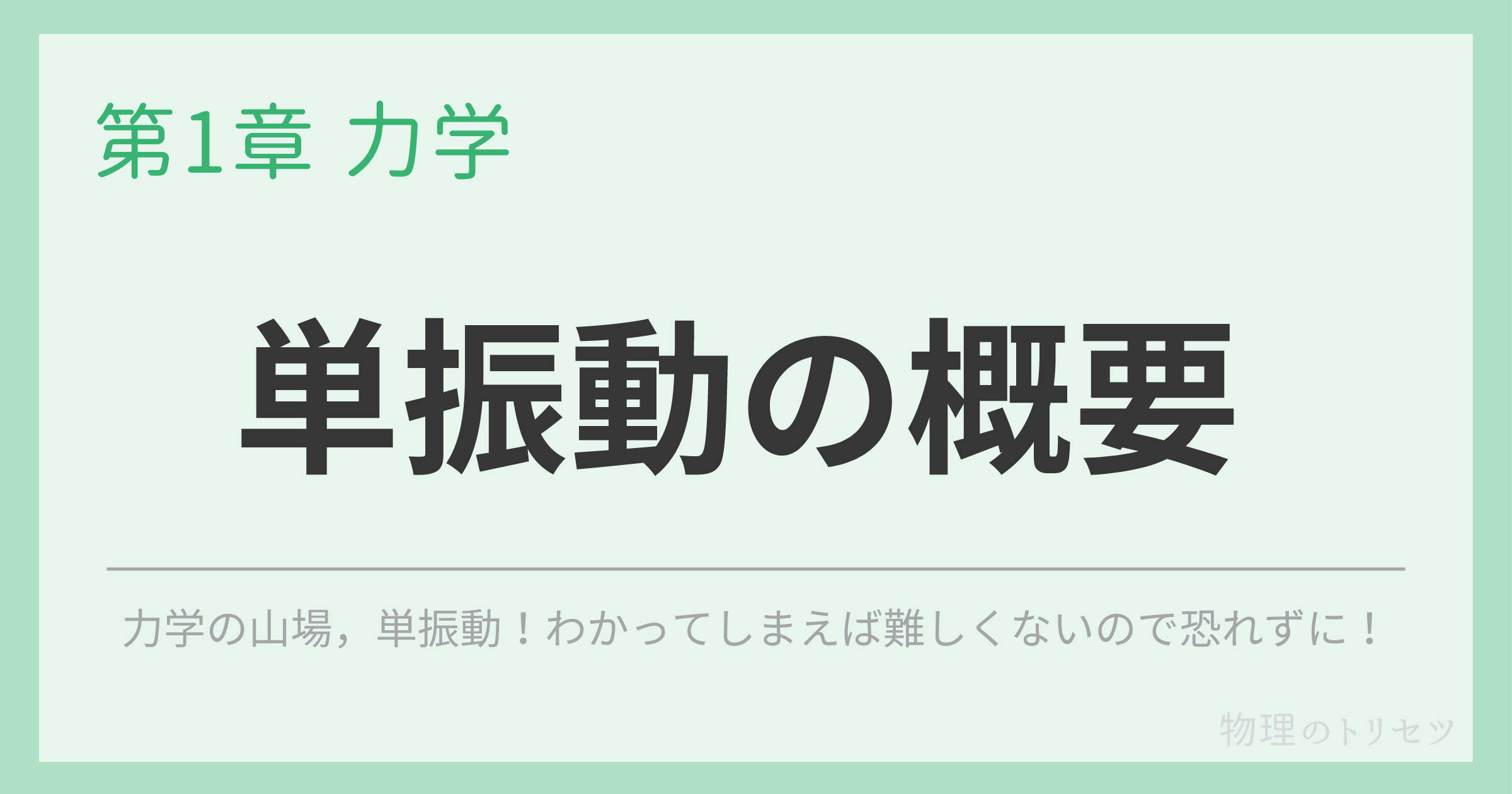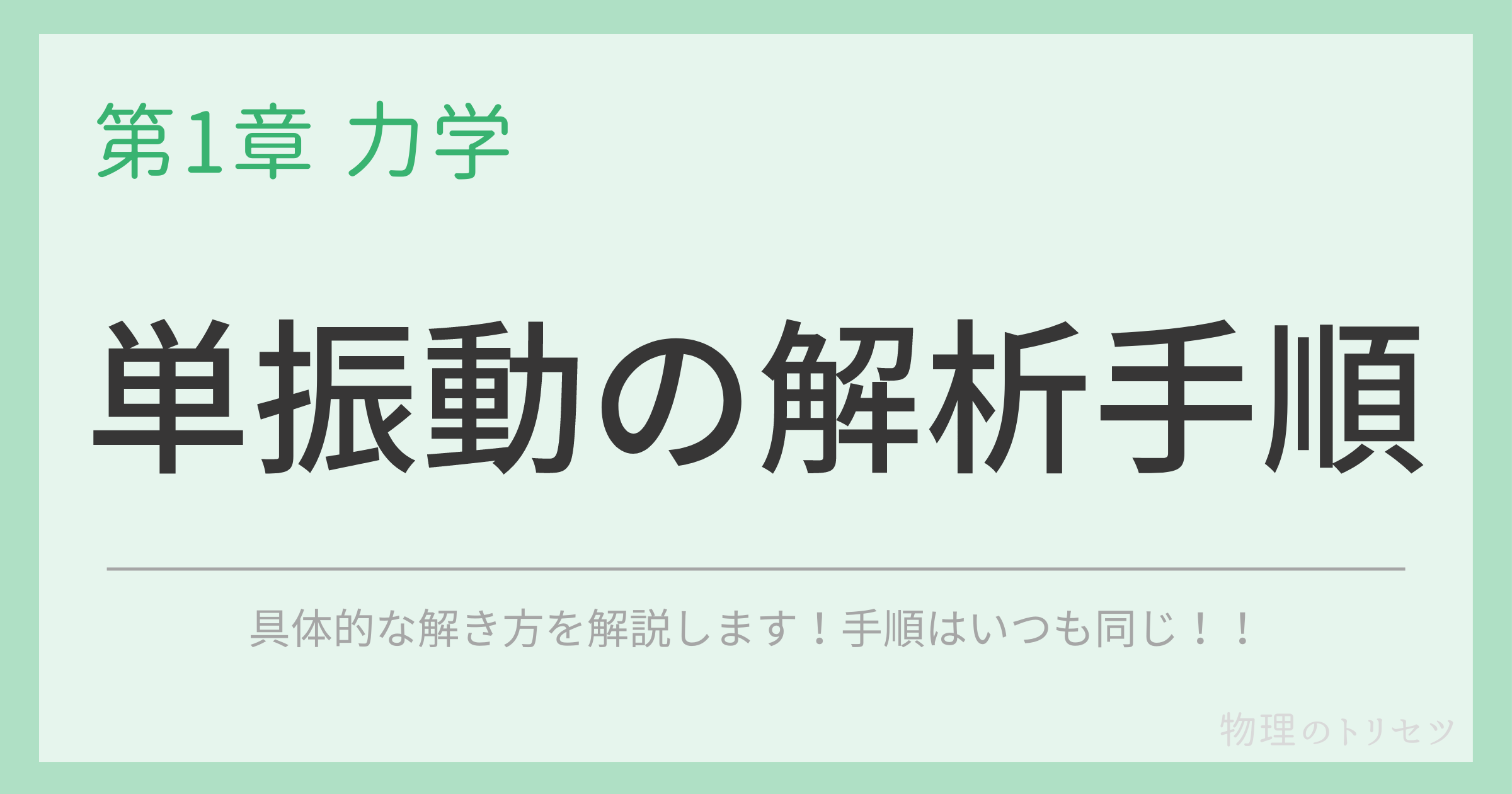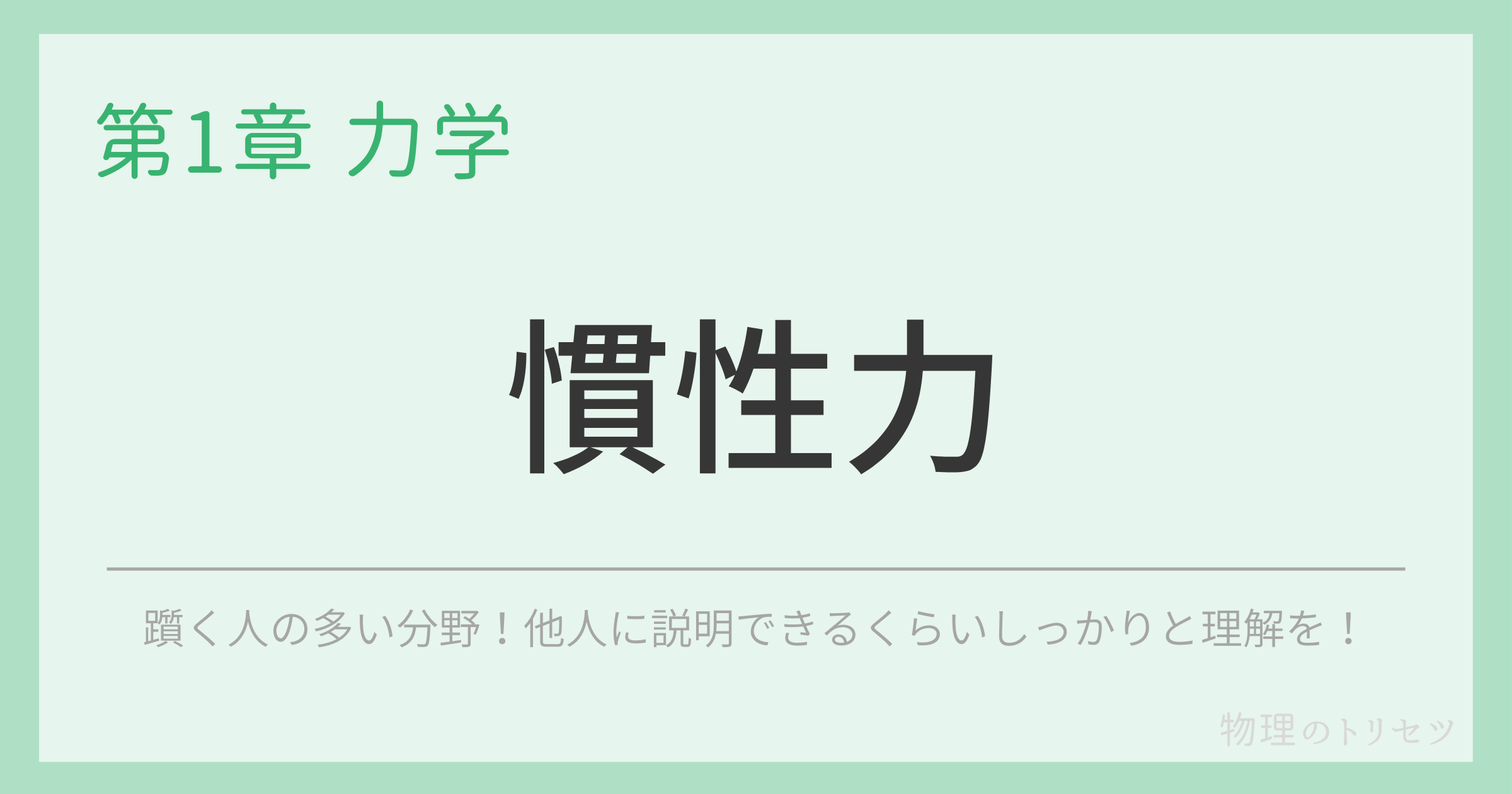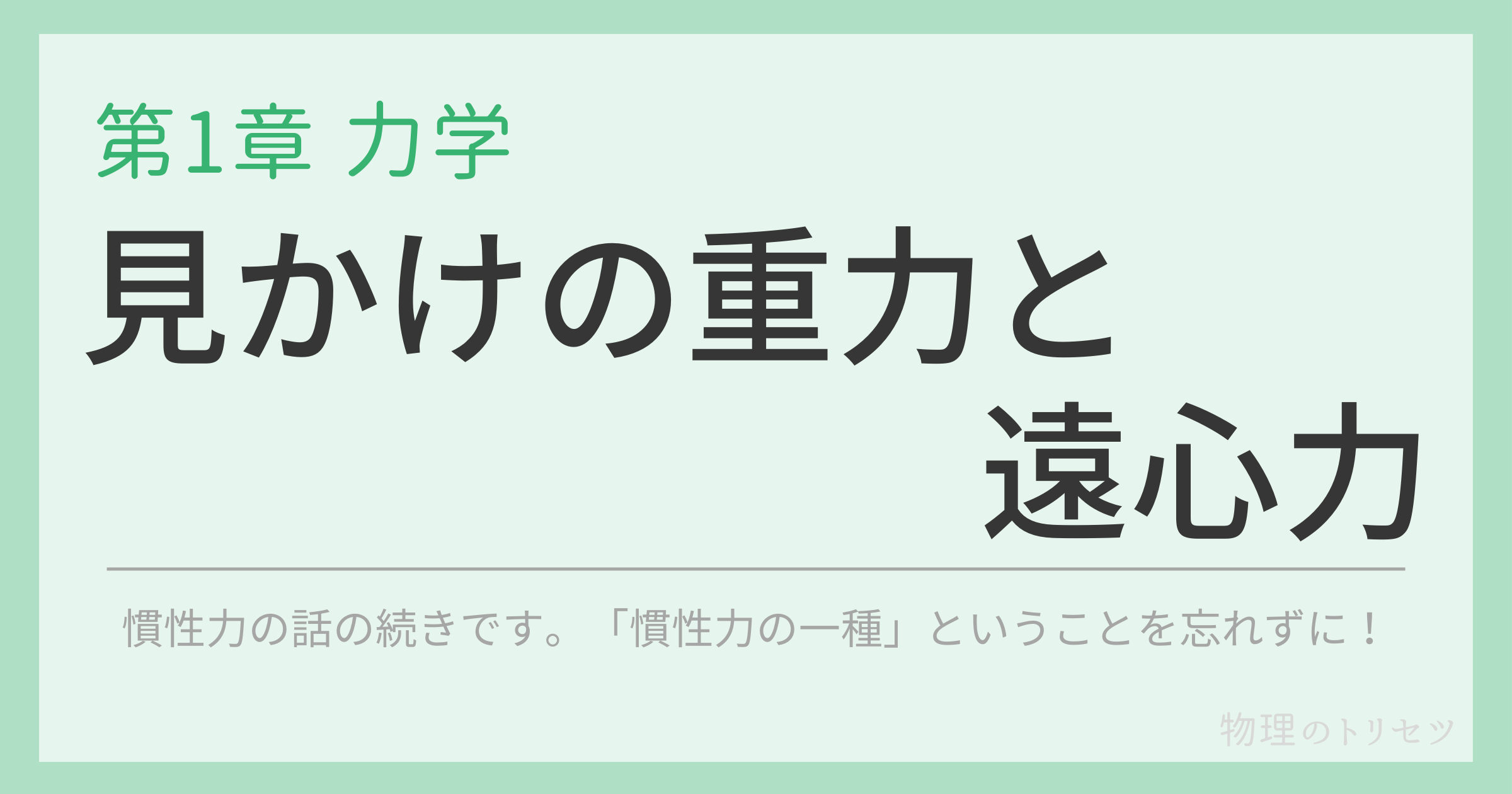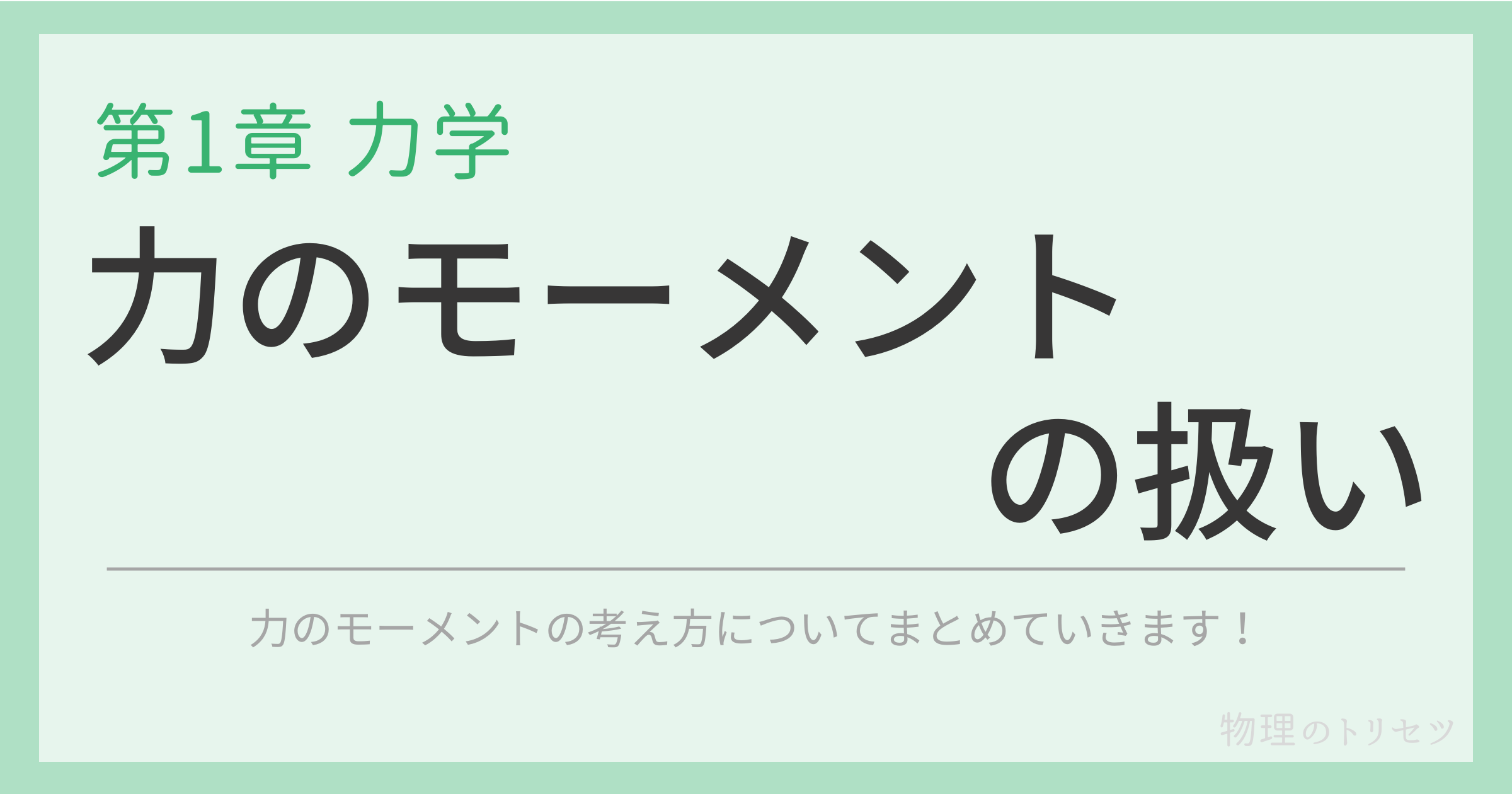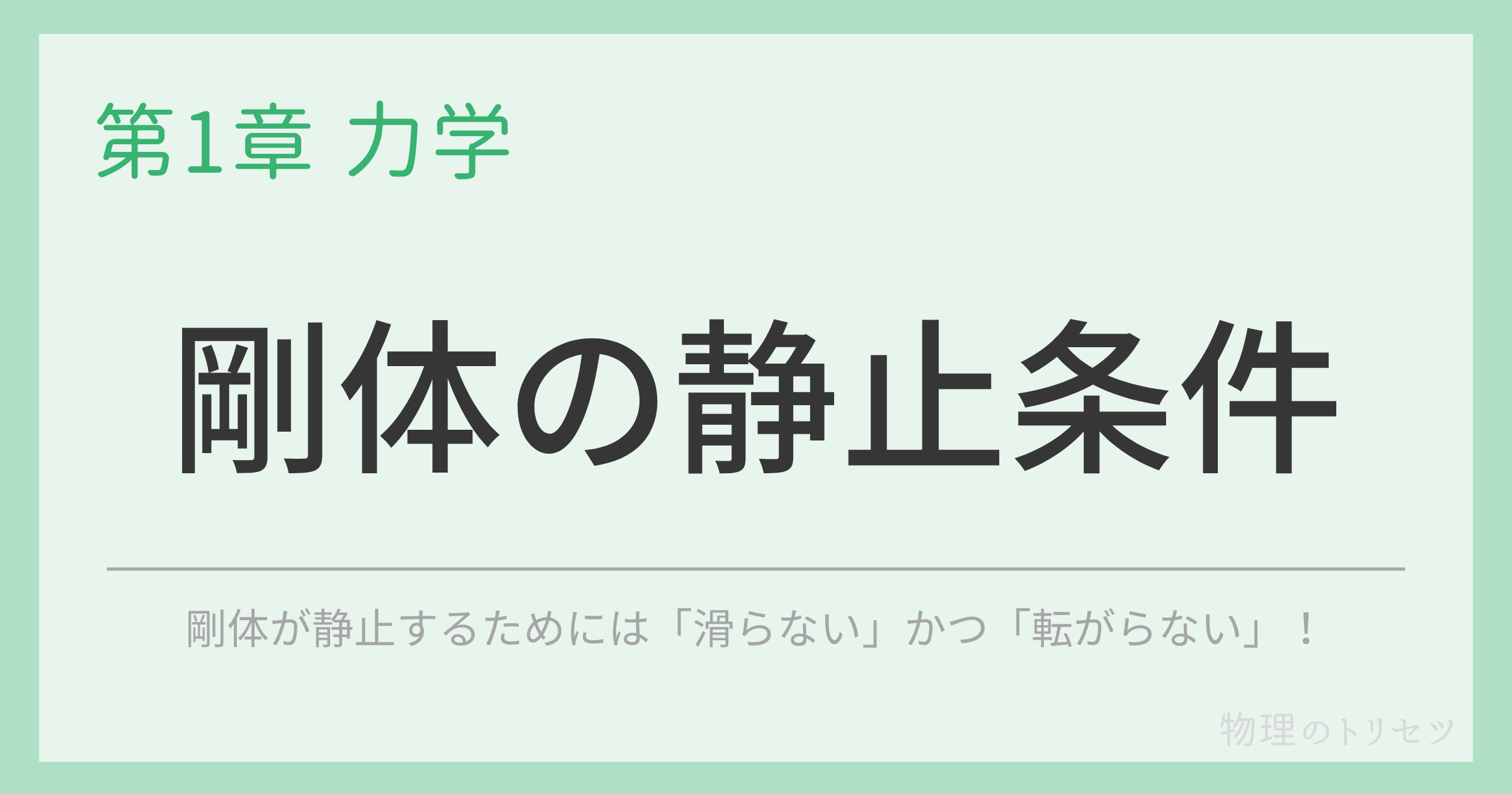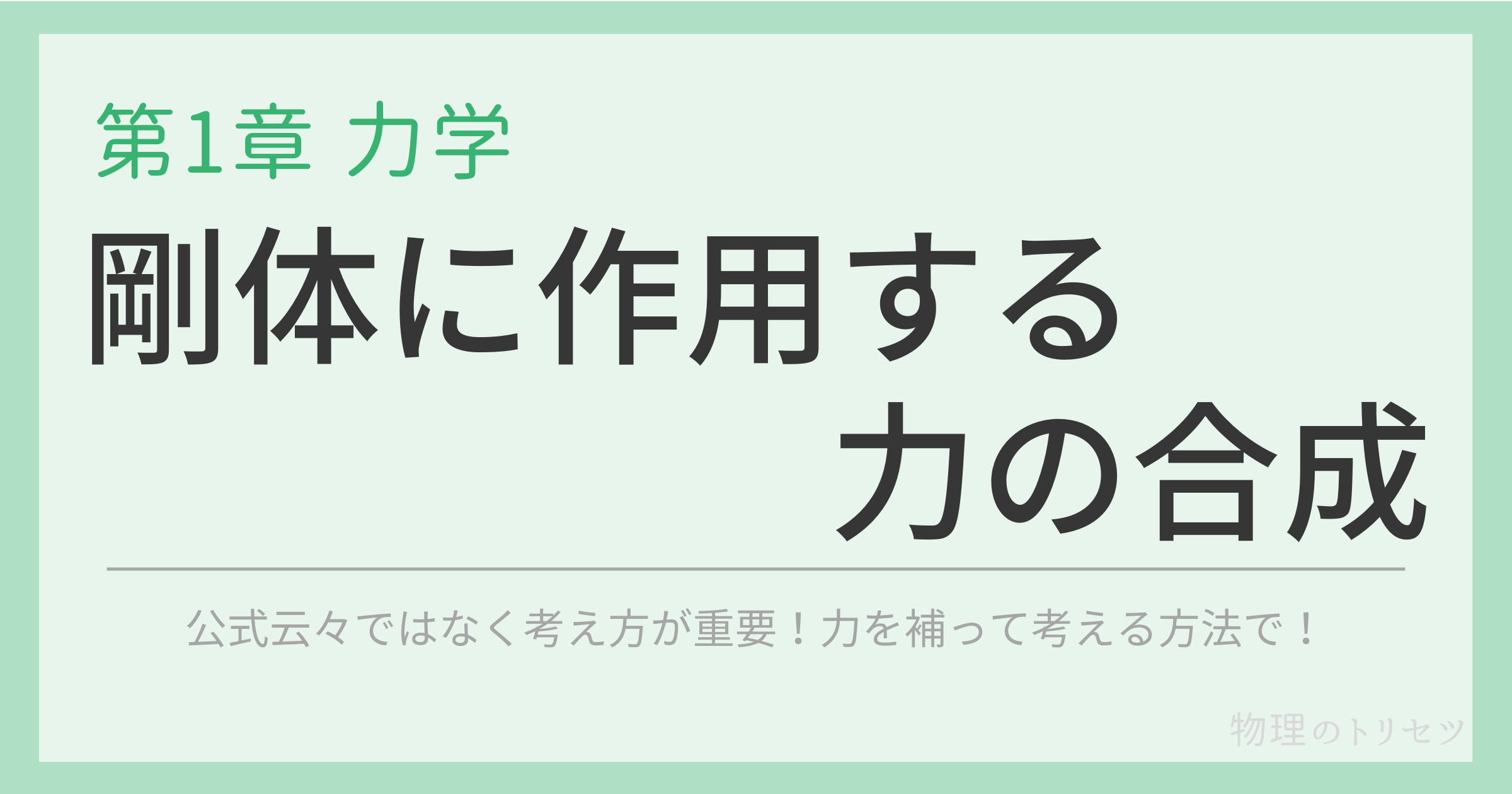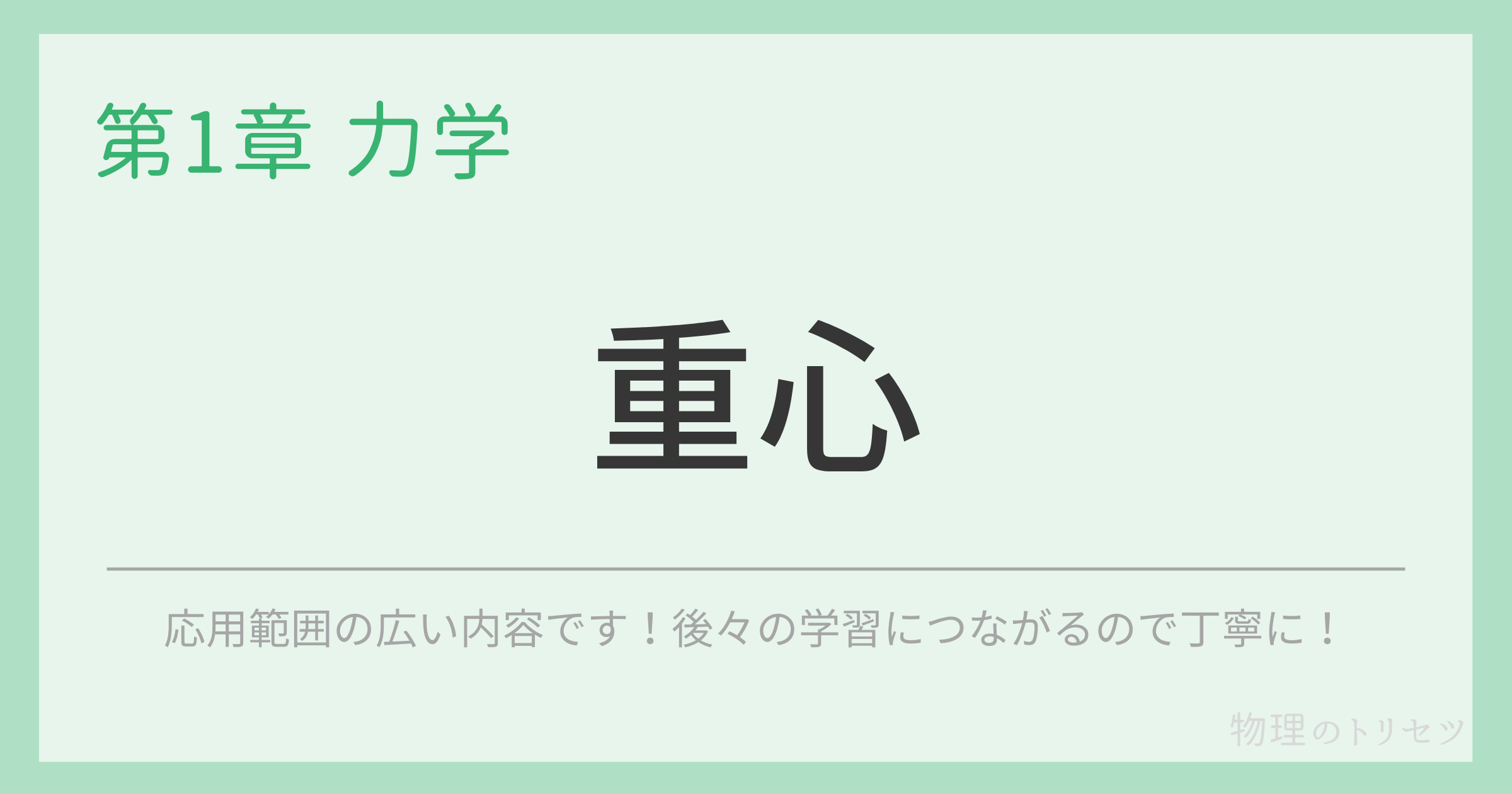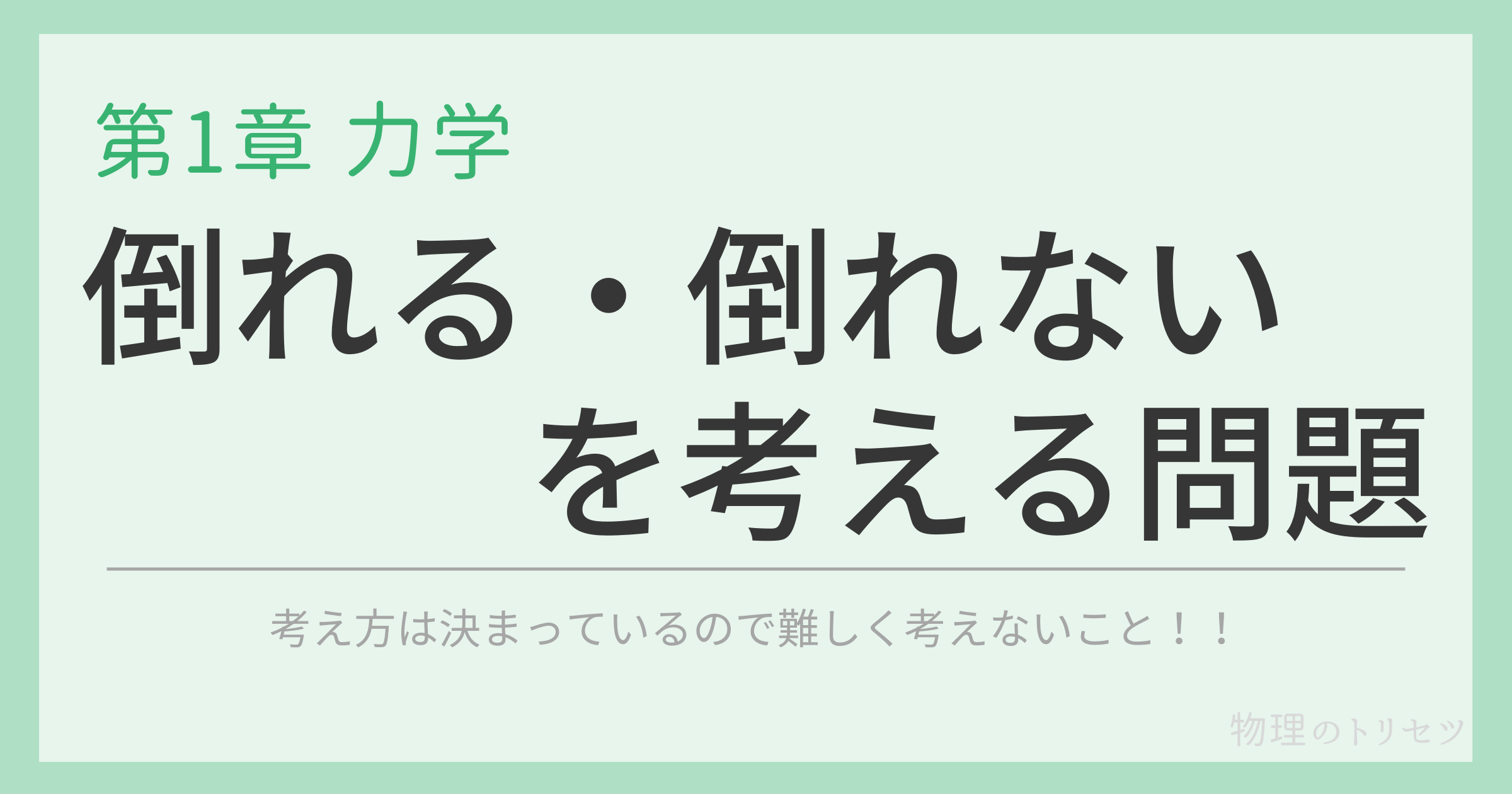2次元空間での運動
速度の合成と相対速度
空気抵抗
滑車における束縛条件
三角台における束縛条件
仕事
位置エネルギー
エネルギー保存則
図で考えるエネルギー保存則
系のエネルギー保存則
運動量と力積
運動量保存則
運動量保存則と2体問題
2物体の衝突と反発係数
壁との衝突における反発係数
円運動 ①
円運動 ②
非等速円運動
単振動の概要
単振動における速度と加速度
単振動の解析手順
単振動のエネルギー保存則
慣性力
見かけの重力・遠心力
万有引力
万有引力の位置エネルギー
ケプラーの法則
惑星運動の問題へのアプローチ
剛体と力のモーメント
力のモーメントの扱い
剛体の静止条件
剛体に作用する力の合成
重心
倒れる・倒れないを考える問題