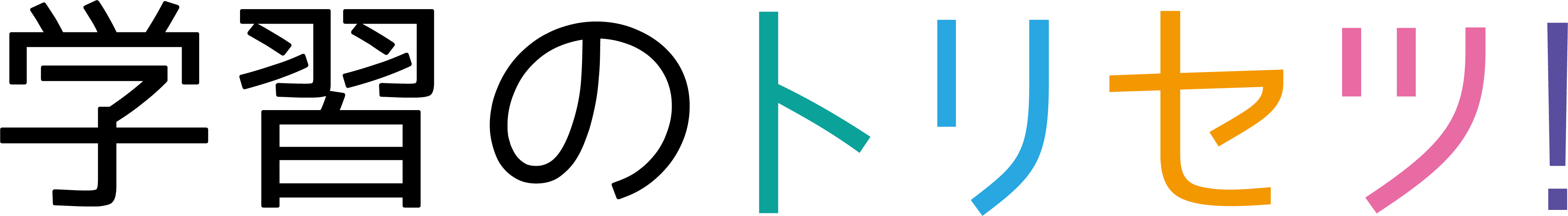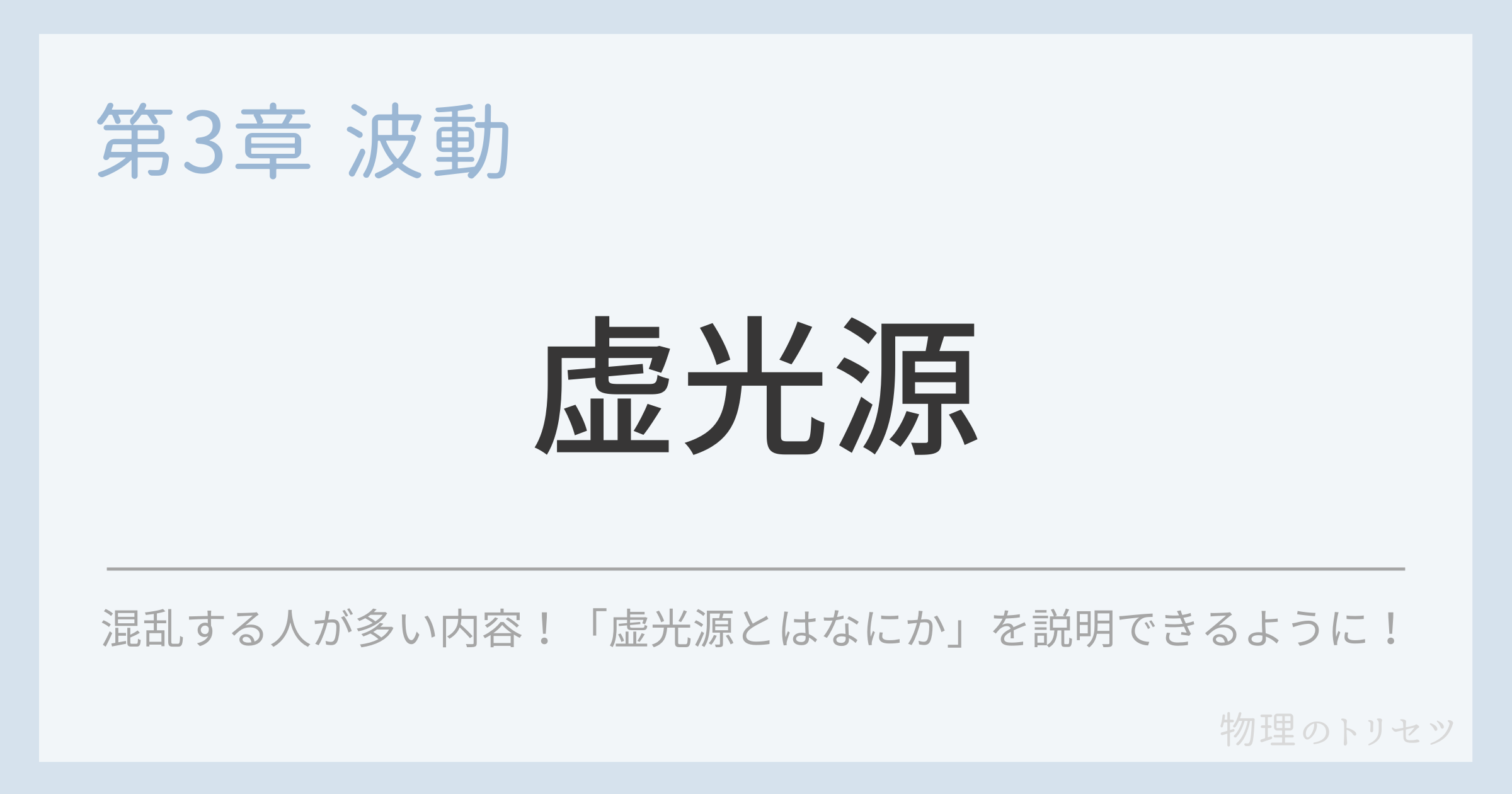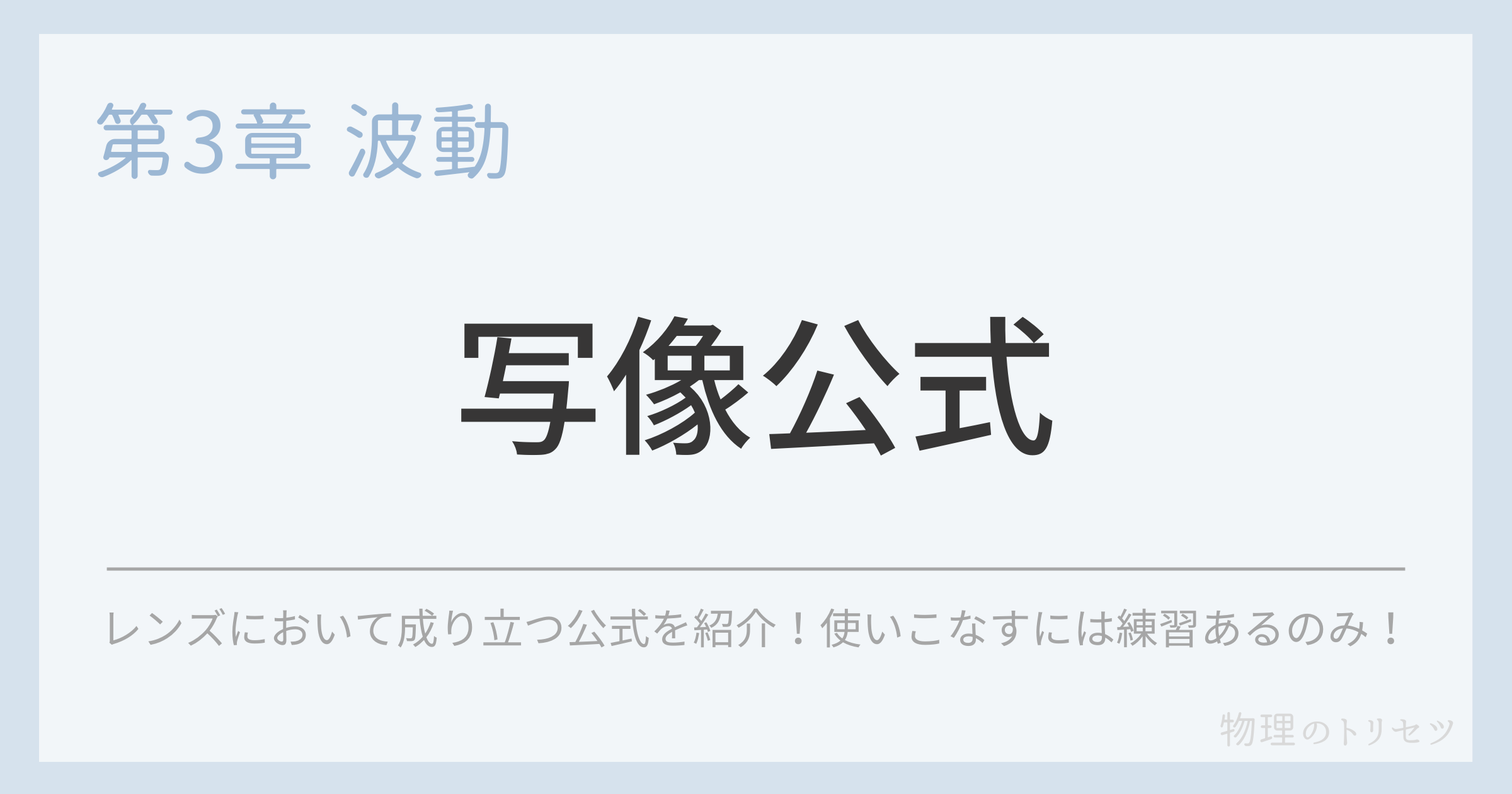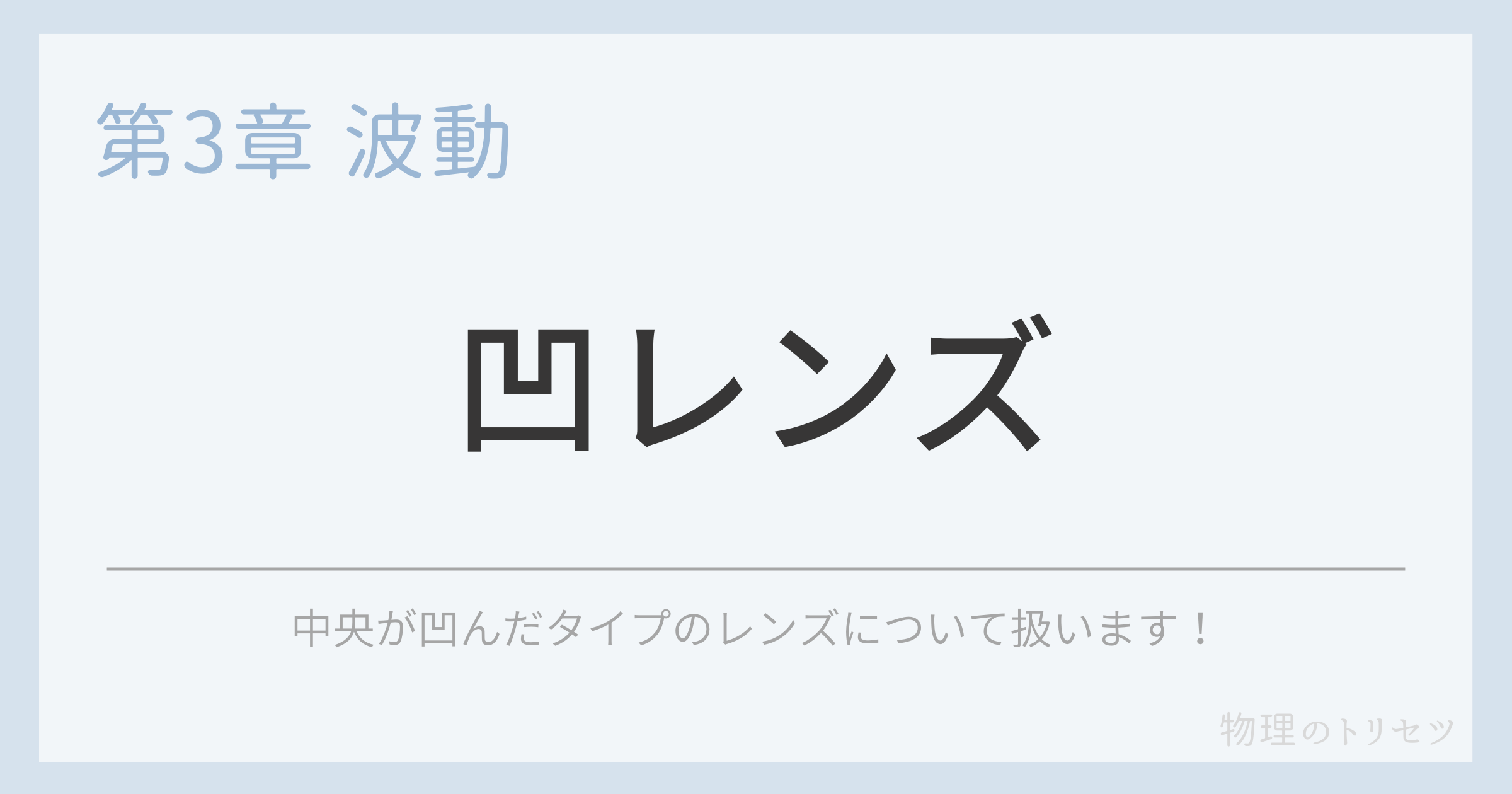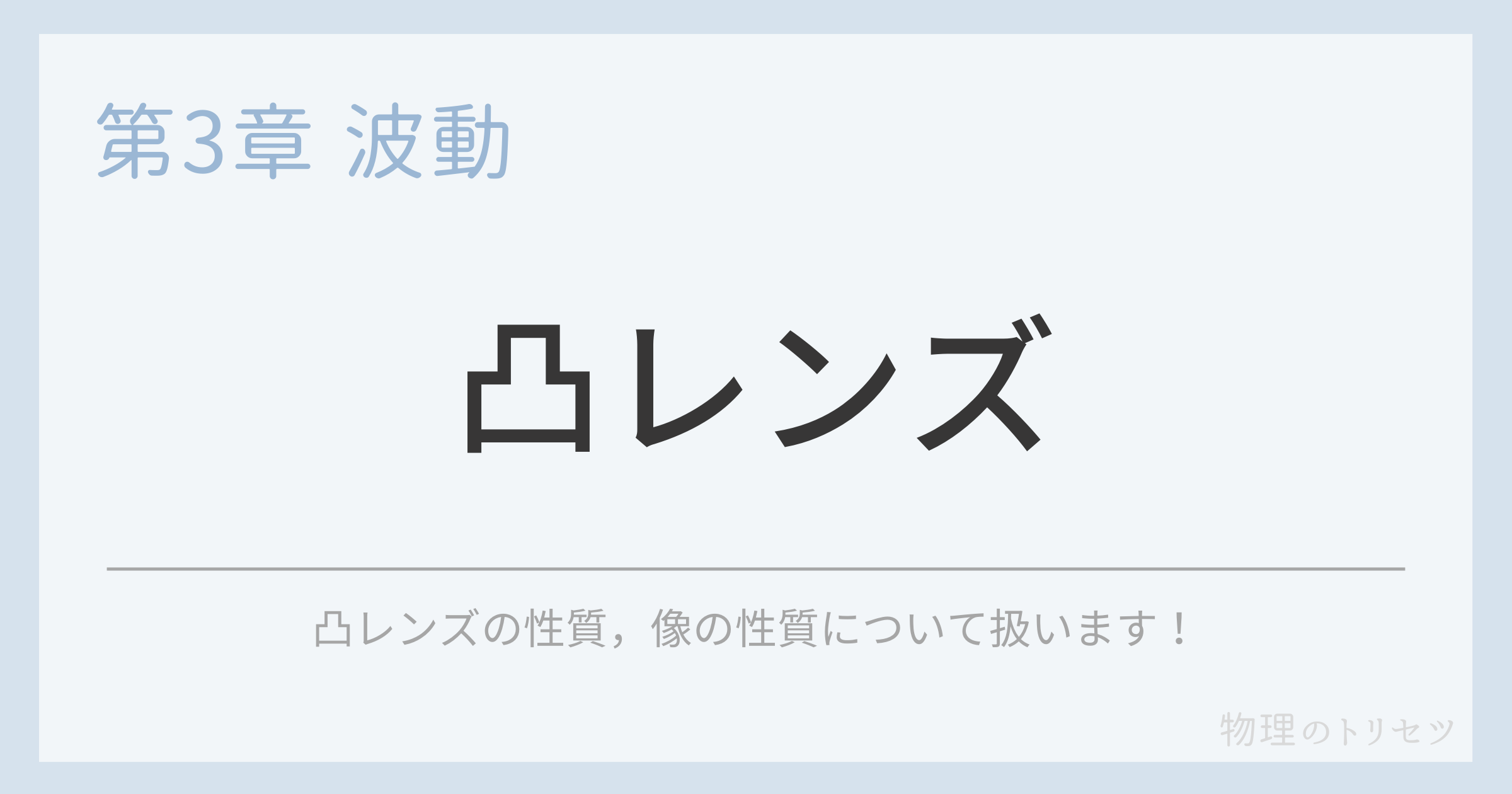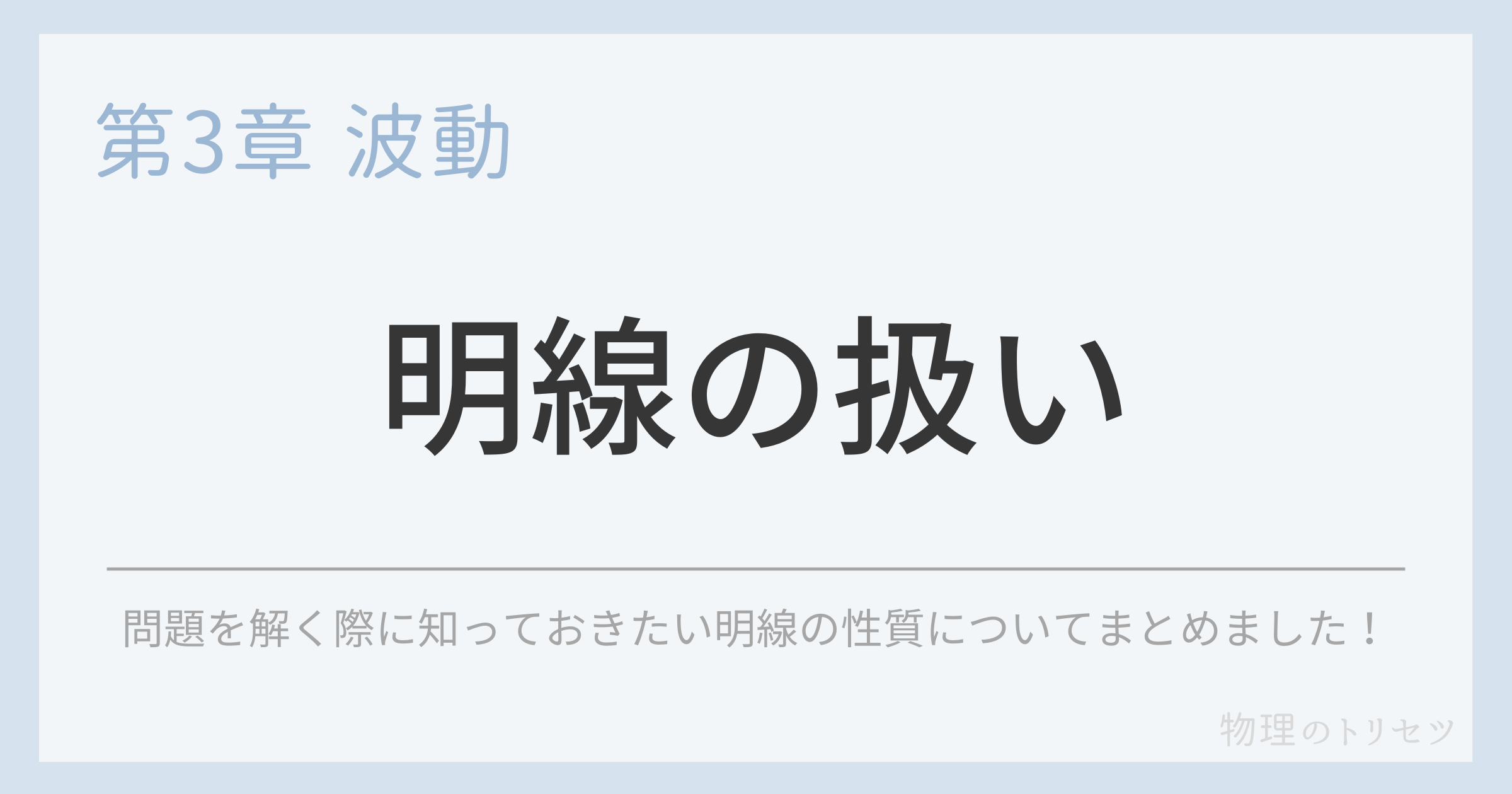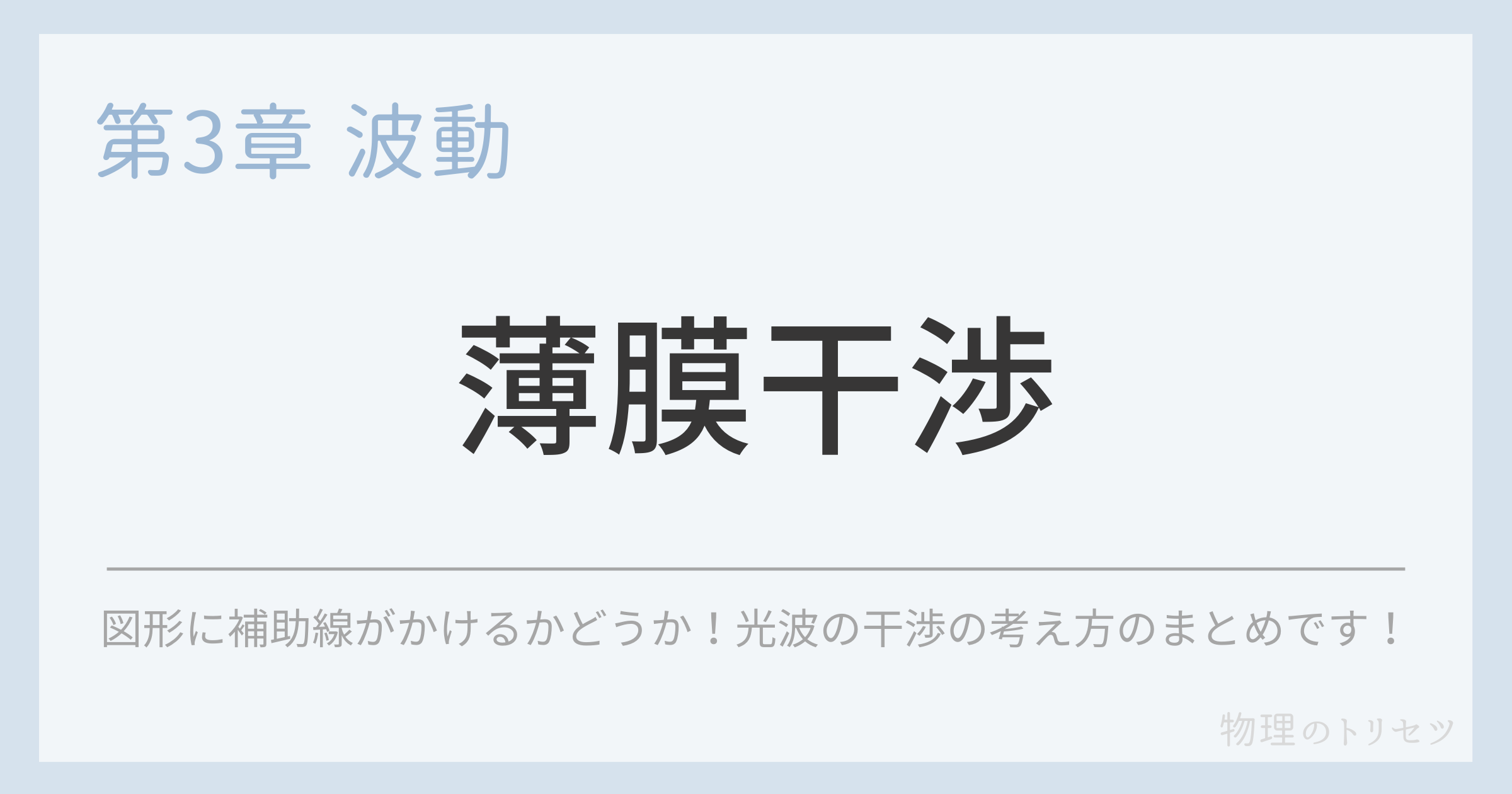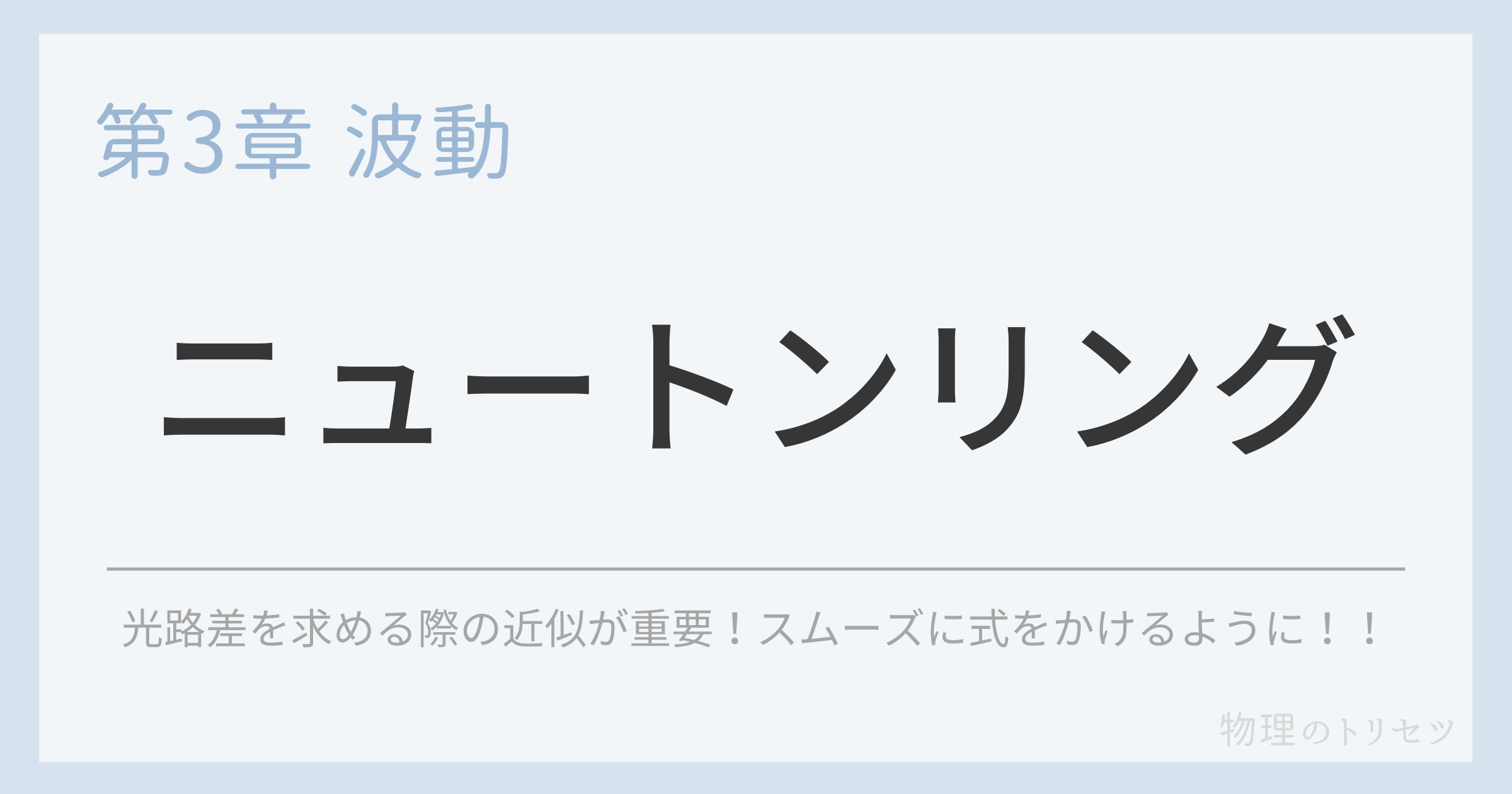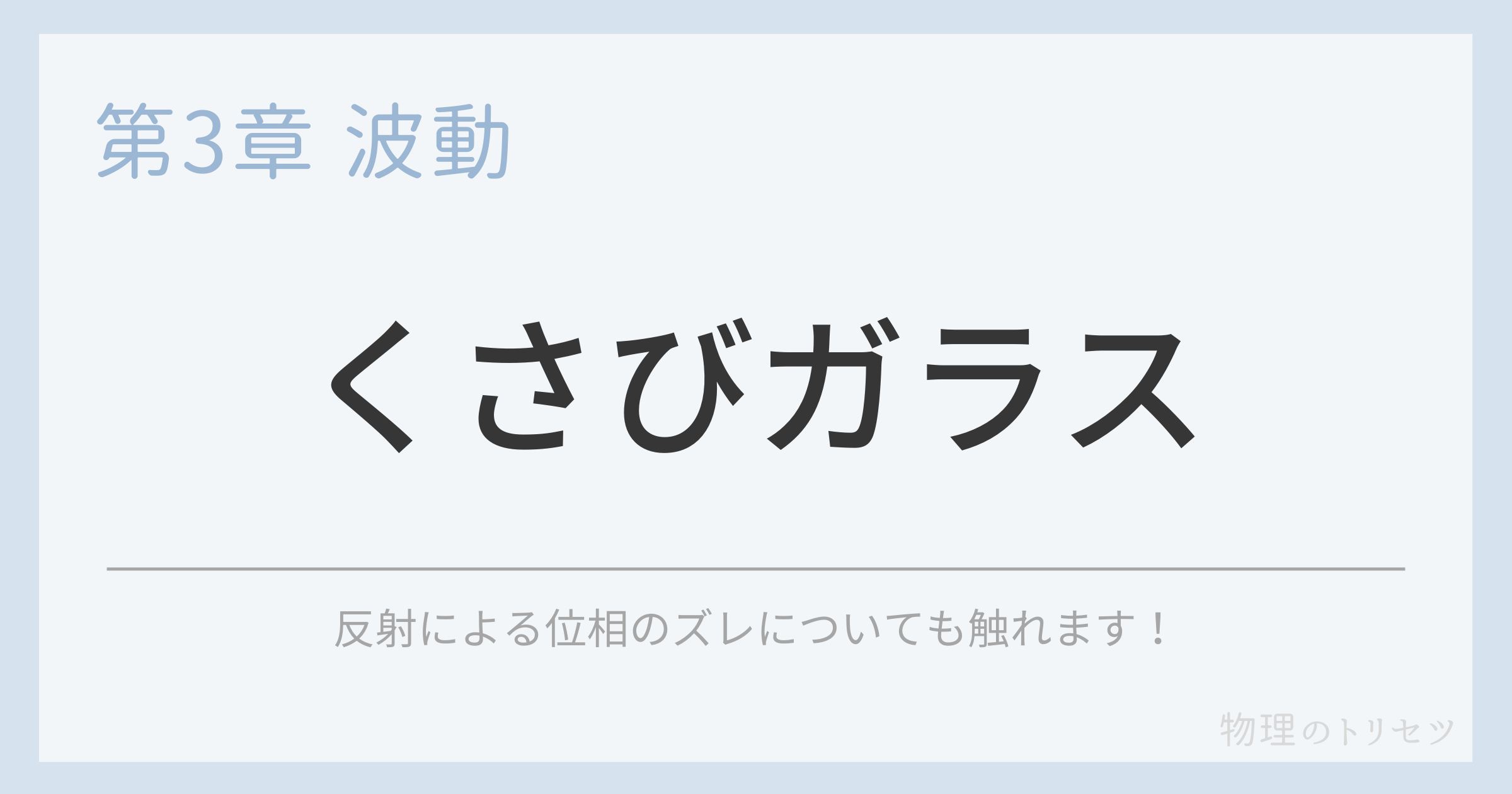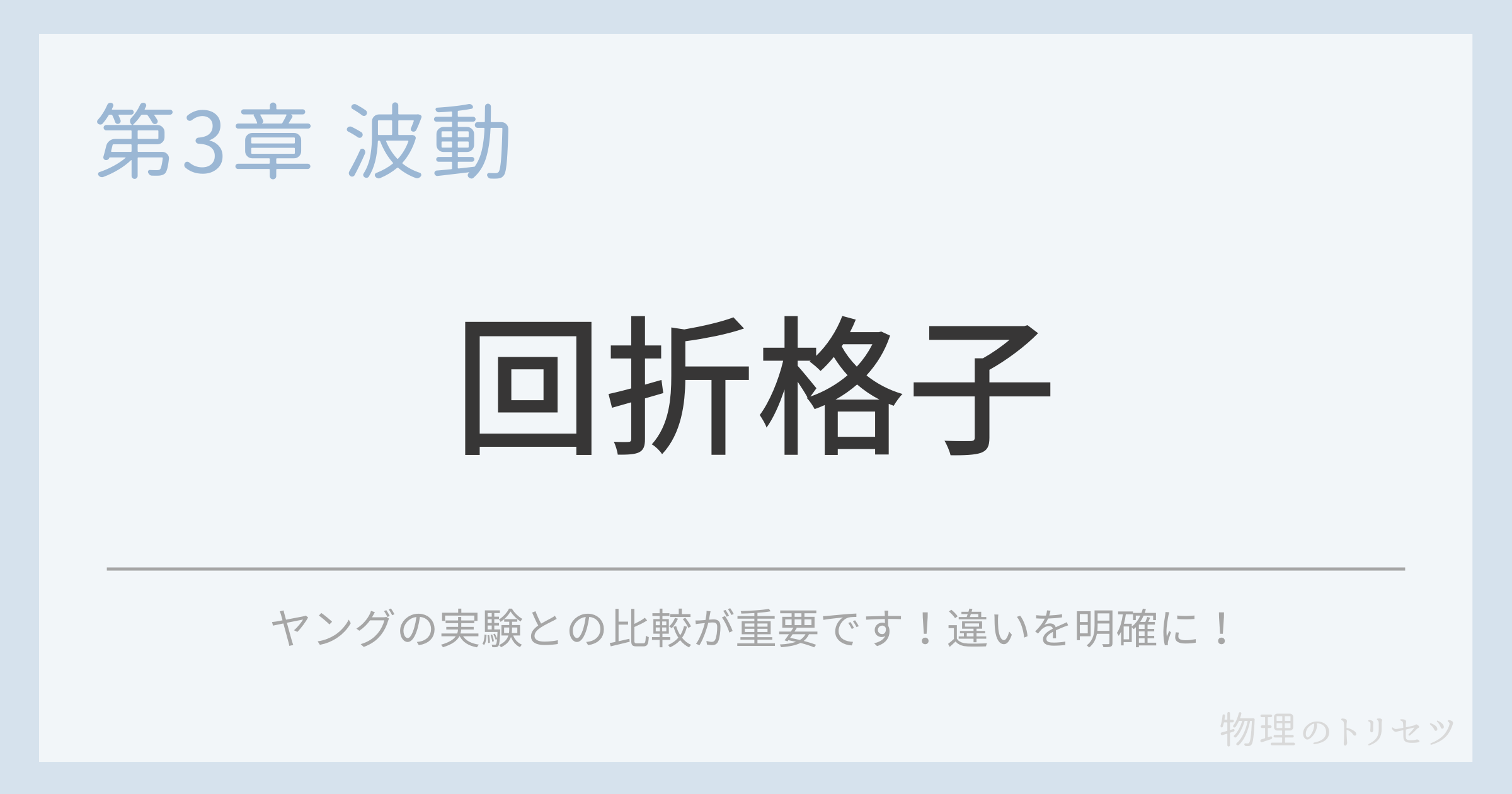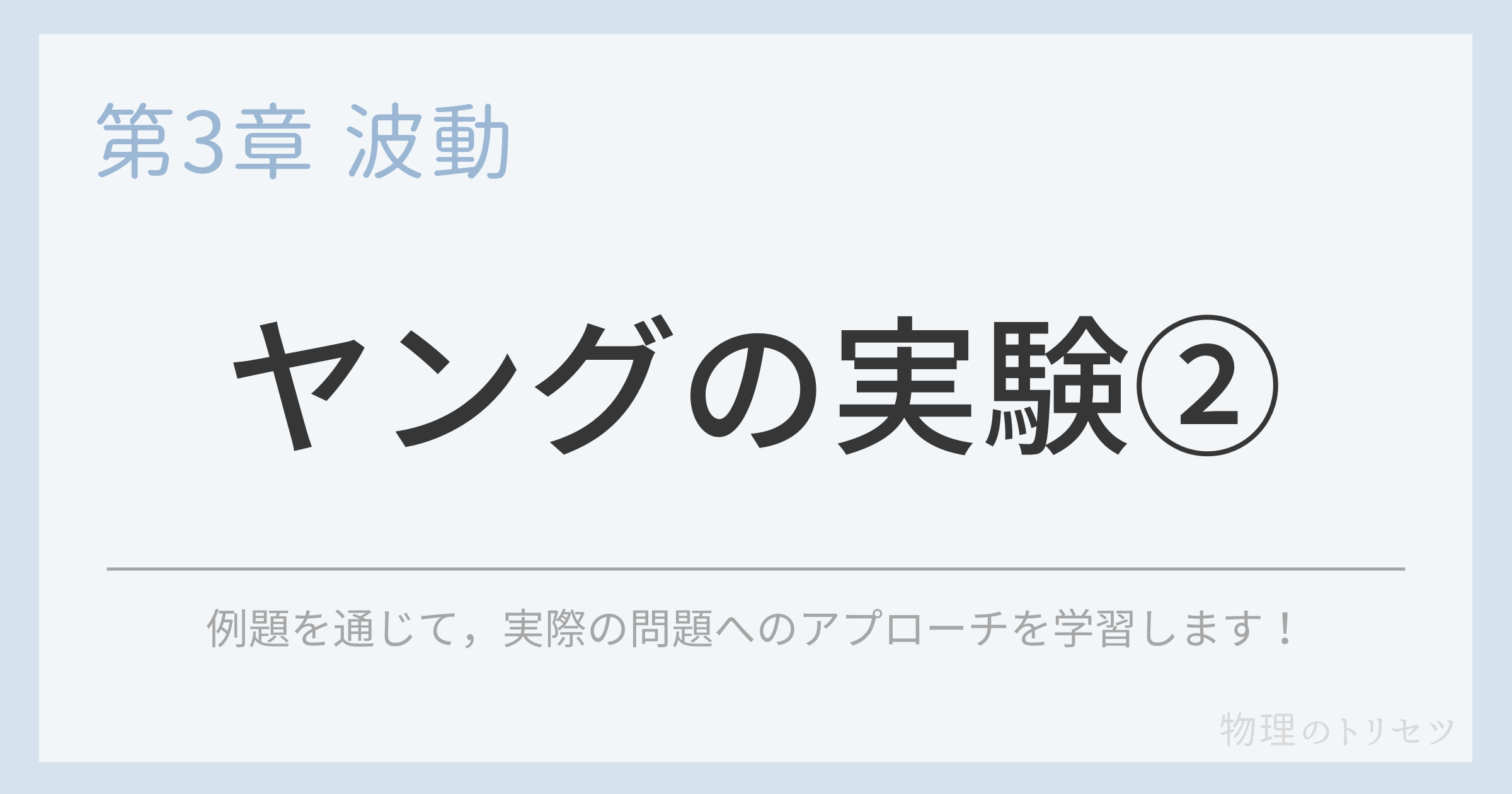-

-
虚光源
合わせレンズ 重なったレンズ 焦点距離が $4.0\cm$ の2枚の凸レンズを次図のように $1.0\cm$ だけ離れた位置に設定した状況を考えてみます。 考え方 左側のレンズに,光軸に平行な光を入射 ...
-

-
写像公式
写像公式 像の場所,大きさ ここまでは,「レンズによってどこに像ができるか」に注目し,作図の方法を中心に説明してきました。 ここからは,「どこにどのくらいの大きさの像ができるか」について考えていきたい ...
-

-
凹レンズ
凹レンズ 性質 凸レンズと異なり,中心部が凹んでいるレンズを凹レンズと呼びます。 光軸は凸レンズと同じように考えます。光軸と平行な光を凹レンズに入射すると,光はレンズの奥で広がります。 まずは「凹レン ...
-

-
凸レンズ
凸レンズの性質 名称の確認 凸レンズは,名前の通り「凸」の形をしたレンズです。 まずはこの凸レンズについて,各名称を確認していきましょう。 レンズの両側の球面の中心を結ぶ直線を光軸と呼びます。 凸レン ...
-

-
明線の扱い
隣り合う明線 明線のおはなし 入試では,「隣り合う明線」について考える問題がよく出題されます。 ある明線($m$ 番目)が強め合いの条件式 $\varDelta D=m\lambda$ を満たしている ...
-

-
薄膜干渉
薄膜干渉とは 膜内に入るまで 空気(屈折率 $1$)から,薄い膜(屈折率 $n$)に,入射角 $i$ で光を入射します。 屈折角を $r$ とし,光の進む向きを2本の直線で表したのが次図です。 左の光 ...
-

-
ニュートンリング
ニュートンリングとは 使用するガラス 同じく2枚のガラスを使うのですが,やや特殊なガラスが登場します。 1枚は平らな普通のガラスの板ですが,もう1枚は片面が球の一部になっている平凸レンズです。「球の一 ...
-

-
くさびガラス
くさびガラス くさびガラスとは 2枚のガラスの板を用意してこれを重ね,片端にだけ紙をはさみます。 大げさに状況をまとめると次図の通りです。 紙は実際には薄いので,ガラス板の間にできる空気の層も非常に狭 ...
-

-
回折格子
回折格子 回折格子とは 一方,ガラス板に平行なスリットを等間隔にたくさん($1000$ 本以上!)並べたものを回折格子と呼びます。 スリットの間隔 $d$ は,格子定数と呼ばれます。 干渉縞について ...
-

-
ヤングの実験②
干渉縞の様子 暗線の位置 ヤングの実験における弱め合いの条件は, $$d\bun{x}{l}=\left(m+\bun12\right)\lambda$$ です。これより,明線の間に暗線が位置すること ...