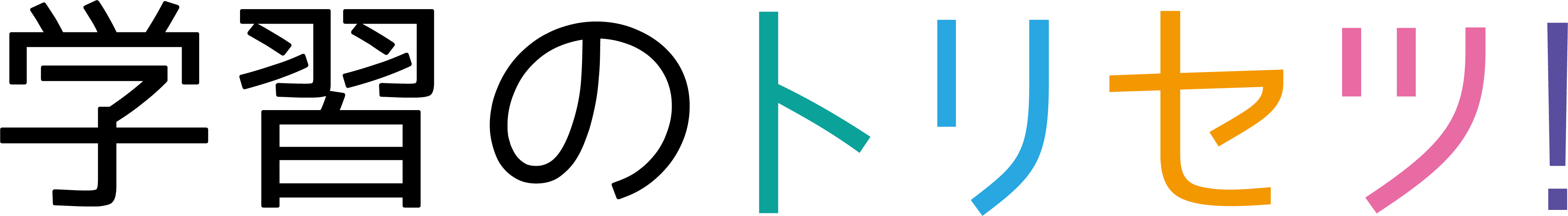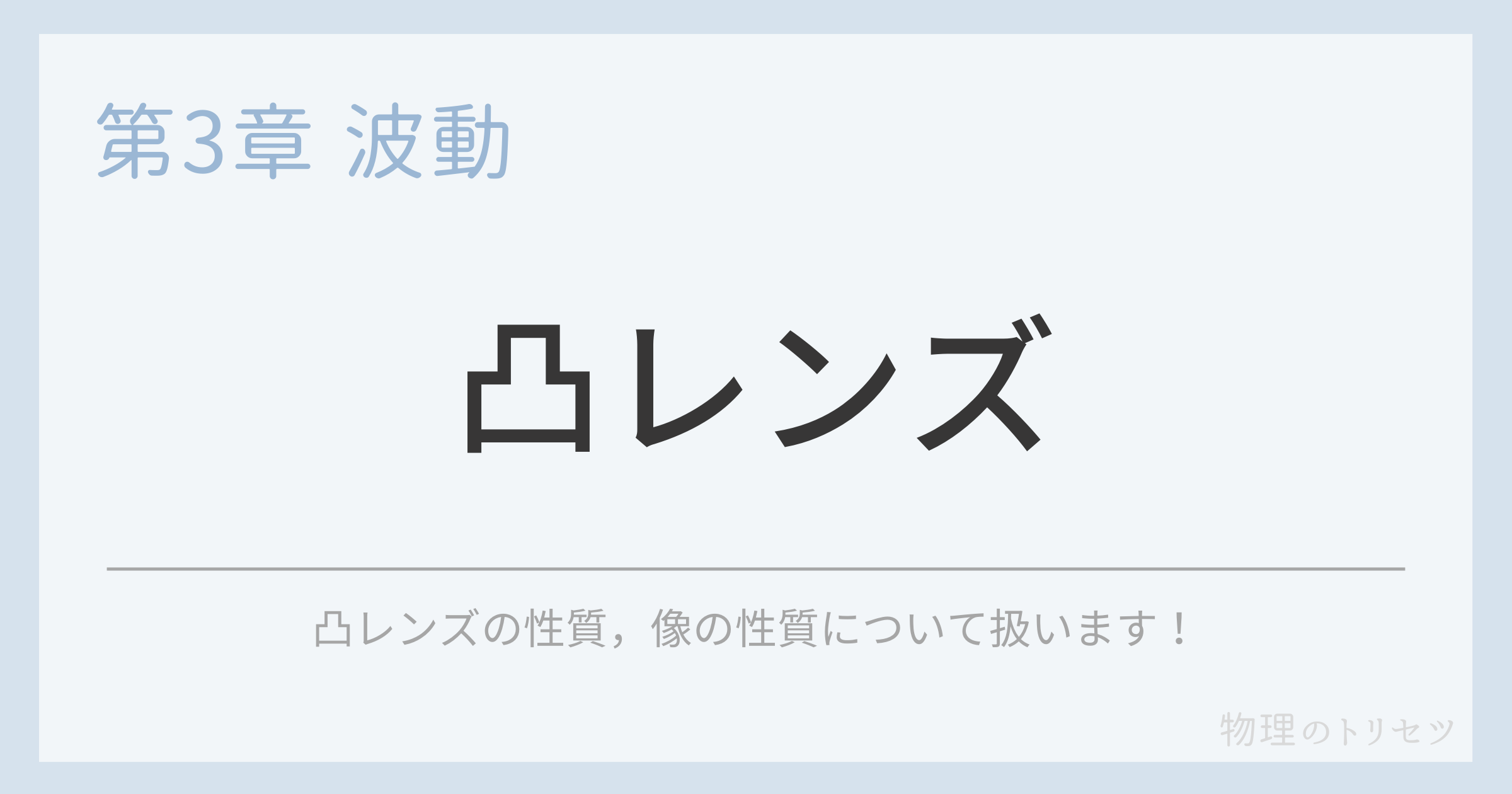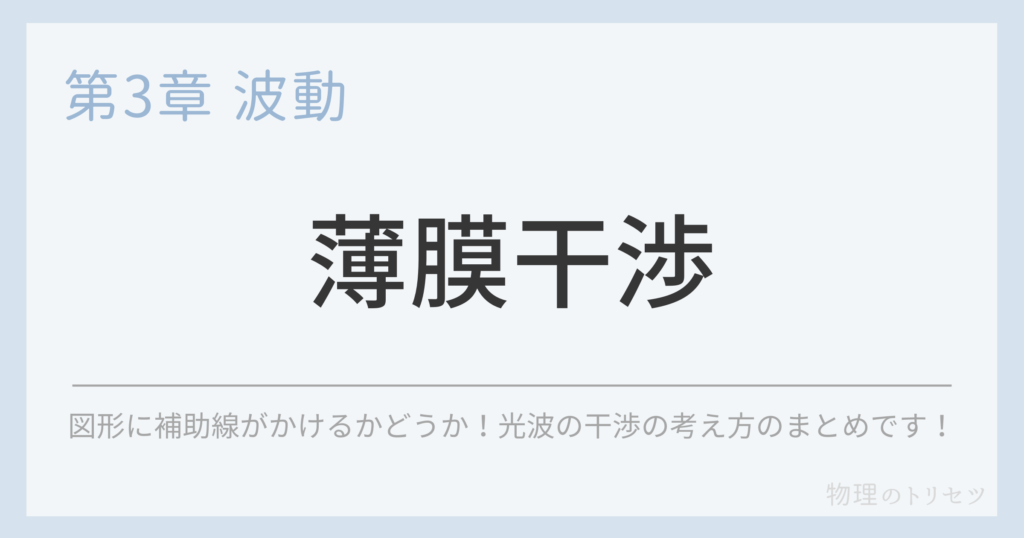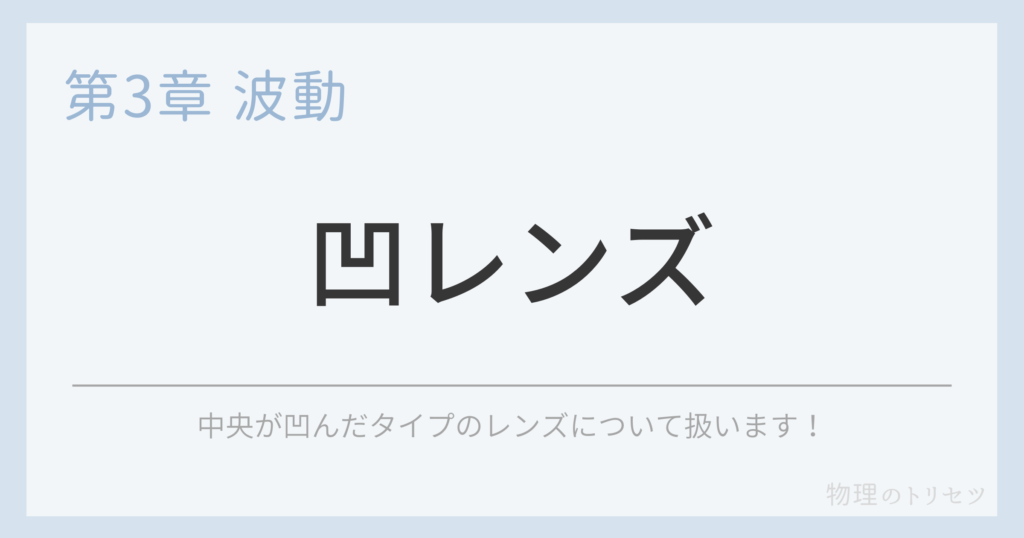凸レンズの性質
名称の確認
凸レンズは,名前の通り「凸」の形をしたレンズです。
まずはこの凸レンズについて,各名称を確認していきましょう。
レンズの両側の球面の中心を結ぶ直線を光軸と呼びます。
凸レンズは,この光軸に平行に入射した光をある1点に集める性質を持ち,この点を焦点と呼びます。
左右対称な形をしているので,レンズの両側に焦点は存在し,レンズの中心から焦点までの距離が焦点距離です。

「凸レンズは広がっている光を,内側に曲げることで1点に集める!」というざっくりとしたイメージが大切です。
なお,光は逆行性という性質を持つため,焦点に光源をおくと,光源から出た光はレンズを通ることで平行な光線になります。
光の進み方
では,凸レンズに平行でない光はどのように進むでしょうか。
.png)
例として,レンズの左側におかれたろうそくを考えてみましょう。
このろうそくの先端の部分から出た光は,様々な方向へと広がりますが,そのうち一部はレンズに向かって進んでいきます。
この光線のうち,「① 光軸に平行な光」は先ほど確認したように,レンズ奥の焦点を通過して直進します。
また,「② レンズの中心を通る光」はそのまま直進します。
図からもわかる通り,これらの光はレンズの奥の1点で交わりますね。
レンズを通過した ①,② 以外の全ての光も,レンズによって曲げられることでこの点を通過します。
まとめ
結局,「ろうそくの先端を出た光は,様々な方向からレンズに入射するが,レンズによって曲げられることである1点に集まる」ことがわかります。
この様子を図示すると次の通りです。
なお,作図の際に必ずしも知っておく必要はありませんが,「③ レンズの手前の焦点を通る光は,レンズを通ると光軸に平行に進む」ことも確認しておくとよいでしょう。

この事実は光の逆行性から確認することができますね。
像
像の仕組み
さて,この「光が集まる点」にスクリーンをおくとどうなるでしょうか?
ろうそくの先端を出た光がこの点に集まるので,ろうそくの先端と同じ色の光がスクリーンに映りますね!
今回はろうそくの先端で考えましたが,ろうそくの他の場所(光の根元,ろうの先端,ろうの根元など…)で考えても同様のことがいえます。
結局,この場所においたスクリーンにろうそくの各点から出た光が集まることで,ろうそくの形が映し出されるのです。
像の種類
これを像と呼びますが,特に今回のように実際にその点に光が集まり,スクリーンに映し出される像のことを実像といいます。
像は上下左右が反転していることが図からわかりますので,特に「倒立実像」と表現するとより正確ですね。
実際に像ができる位置を調べる際には,① の光と ② の光のみに注目して,その交点を求めるだけで十分です。
虚像
焦点との位置関係
続いて,レンズ手前のろうそくが焦点よりレンズの近くにおかれている状況を考えてみましょう。
像の位置を調べるためには,先ほどと同様に ① と ② の光を図示する必要があります。
実際に図示したのが上図ですが,レンズの奥で交わらないですね。
よって,実際に光が集る場所が存在しないため,どこにスクリーンをおいても像が映し出されることはありません。
奥から眺める

では,この光をレンズの奥から眺めてみるとどうでしょうか?
人間は「光はまっすぐ進むもの!」と思い込んでいるため,① と ② の光をレンズの手前に延長した交点 $\rmP$ から,2本の光線がまっすぐ進んできたように知覚します。
実際には図のようにレンズによって曲げられた光を見ているのですが,$\rmP$ 点から光がまっすぐ進んできている状況と区別できないのです…!
虚像
ろうそくの先端以外についても同様のことがいえるので,「レンズの奥から眺めると,$\rmP$ 点に先端が位置するような大きなろうそくがレンズの手前にあるように見える」という現象が起こります。
この像は,「レンズの奥から見るとあたかもあるかのように見える像」であり,実際にスクリーンに映し出されるわけではないため,虚像と呼ばれます。
図の虚像は上下左右が反転していないため,「正立虚像」と表現するとより正確です。
像のまとめ
実像と虚像
実像は実際にレンズの奥に光が集まってできるのに対し,虚像はレンズの奥から眺めることでレンズ手前にあるかのように見えるという違いがあります。
これより,「実像は必ずレンズの奥に,虚像は必ずレンズの手前にできる」ことがわかりますね。
さらに,レンズの手前か奥かによらず,レンズを通過した直後の光(の延長線)が集まる点が像と考えることができます。