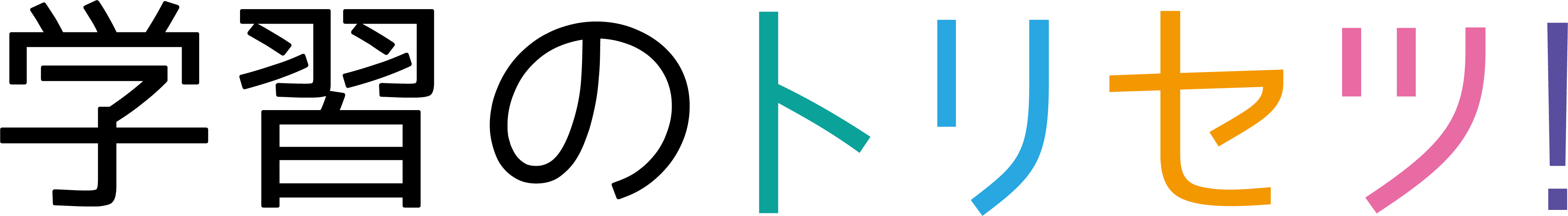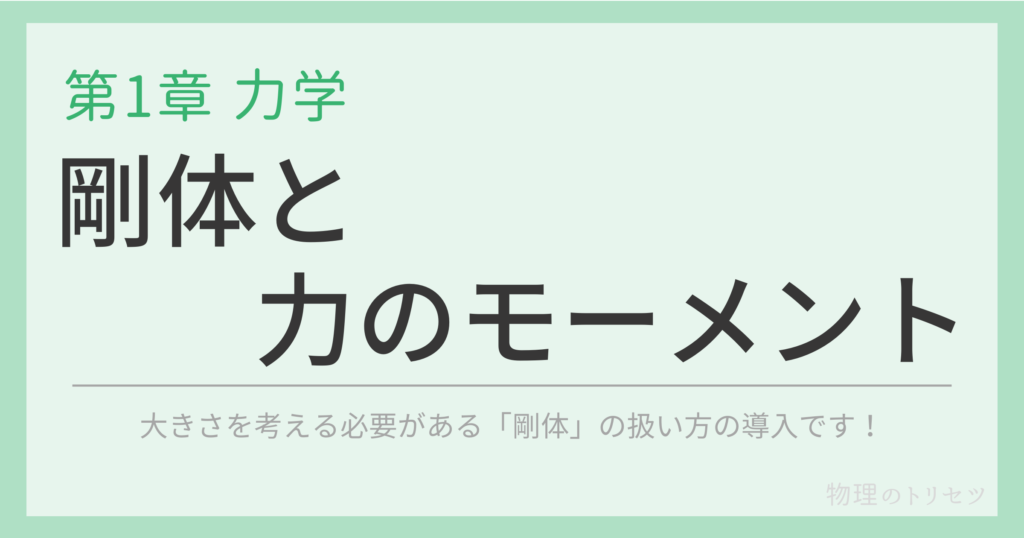惑星運動の問題の解き方
基本方針
注目する惑星の軌道が円か楕円かで方針が大きく異なります。基本的な問題は以下の方針で解き進めることができます。
惑星運動の問題の解き方
円軌道の場合
向心方向の運動方程式を立式する。周期は,$T=\bun{2\pi r}{v}$ で求める。
楕円軌道の場合
近日点と遠日点で,ケプラーの第二法則と力学的エネルギー保存則を立式する。
周期はケプラーの第三法則を用いて求める。比較する惑星がない場合は,楕円の面積を面積速度で割ることで周期を求める。
なかなかイメージしづらいと思いますので,例題を通じて解き方を確認していきましょう。
例題
太陽の中心を焦点の1つとして,地球は公転している。太陽から近日点,遠日点までの距離をそれぞれ $r_1,\,r_2$ とする。太陽の質量を $M$,万有引力定数を $G$ として,以下の設問に答えよ。
近日点および遠日点における地球の速さ $v_1,\,v_2$ をそれぞれ求めよ。
地球の公転周期$T$ を求めよ。ただし,楕円の面積が $S=\Bun{\pi(r_1+r_2)\sqrt{r_1r_2}}{2}$ で与えられることを利用してよい。
(1) の解き方
惑星が楕円軌道を描いて運動していますので,面積速度保存則と力学的エネルギー保存則の連立という定石通りの解法になります。
面積速度については,図のように「太陽と惑星を結ぶ直線(動径)と,速度ベクトルが作る三角形」をかいて考えるとわかりやすいですね。
近日点の面積速度は $\bun12r_1v_1$,遠日点の面積速度は $\bun12r_2v_2$ ですので,面積速度保存則より,
$$\Bun12r_1v_1=\bun12r_2v_2$$が得られます。
力学的エネルギー保存則についても,近日点と遠日点で,
$$\Bun12mv_1\!^2-G\bun{mM}{r_1}=\bun12mv_2\!^2-G\bun{mM}{r_2}$$と立式できますね。
これら2式を連立することで,
$$v_1=\sqrt{\bun{2GMr_2}{r_1(r_1+r_2)}},\ v_2=\sqrt{\bun{2GMr_1}{r_2(r_1+r_2)}}$$が得られます。
答えの確認
立式している面積速度保存則と力学的エネルギー保存則に対称性があるため,$v_1$ の $r_1$ を $r_2$ に,$r_2$ を $r_1$ に変えたときに $v_2$ となることを確認できると計算ミスを減らすことができます。
(2) の解き方

面積速度が「惑星と太陽を結ぶ線分が単位時間あたりに掃く面積」だったことを思い出しましょう。
楕円の面積が単位時間あたりに面積速度ずつ塗りつぶされていくわけですね。
楕円を全て塗り終えるとちょうど地球が公転を終えることになりますので,楕円の面積を面積速度で割ることで周期が得られます。
よって求める周期は,
$$T=\bun{S}{\bun12r_1v_1}=\bun{\pi(r_1+r_2)}{\sqrt{2GM}}$$です。
$\bun{S}{\bun12r_2v_2}$ で計算しても当然同じ結果になります。
楕円について
面積の計算

上の例題では楕円の面積が与えられていましたが,自力で求める必要がある場合もありますので手順を理解しておきましょう。
まず,楕円とは「平面上のある2点からの距離が一定の点の集合」です。この2点が焦点と呼ばれていて,そのうち片方の点に太陽が存在することになります。
物理では,近日点距離 $r_1$ と遠日点距離 $r_2$ が与えられます。一方,楕円の長半径 $a$,短半径 $b$ を用いて,楕円の面積は $\pi ab$ と表されることが知られています。
よって,物理では以下を自力で計算できるようにしておくことが目標です。
目標
近日点距離 $r_1$,遠日点距離 $r_2$ を用いて,楕円の面積 $\pi ab$ を求める。
長半径 $a$,短半径 $b$ についてそれぞれ考えていきます。
長半径 $a$ について
右図から,$r_1+r_2$ と $2a$ が等しいことがわかります。よって,
$$a=\bun{r_1+r_2}{2}$$として長半径 $a$ が求まります。
短半径 $b$ について
まず,図の$\rmA$点について考えます。2焦点から$\rmA$点までの距離の和は,$\rmA\rmF+\rmA\rmF\mskip 1mu\prime $ ですが,$\rmA\rmF=\rmF\mskip 1mu\prime \rmA\mskip 1mu\prime $ であるため,
$$\rmA\rmF+\rmA\rmF\mskip 1mu\prime =\rmF\mskip 1mu\prime \rmA\mskip 1mu\prime +\rmA\rmF\mskip 1mu\prime =\rmA\rmA\mskip 1mu\prime =r_1+r_2$$となります。
この距離は $\rmB\rmF+\rmB\rmF\mskip 1mu\prime $ でも等しくなりますが,$\rmB\rmF=\rmB\rmF\mskip 1mu\prime $ ですので,
$$\rmB\rmF=\bun{r_1+r_2}{2}$$ですね。
続いて,$\rmF\rmO$ ですが,対称性から明らかに $\rmF\rmO=\rmO\rmF\mskip 1mu\prime =\bun{FF\mskip 1mu\prime }{2}$ ですね。
$$\begin{aligned}\rmF\rmF\mskip 1mu\prime &=\rmA\rmA\mskip 1mu\prime -\rmA\rmF-\rmF\mskip 1mu\prime \rmA\mskip 1mu\prime \\&=\rmA\rmA\mskip 1mu\prime -2\rmA\rmF\\&=2a-2r_1\\&=r_2-r_1\end{aligned}$$が成り立つので,$\rmF\rmO=\bun{r_2-r_1}{2}$ であることがわかります。
直角三角形$\rmF\rmB\rmO$で三平方の定理を用いることで,
$$\begin{aligned} \rmF\rmB^2=\rmF\rmO^2+\rmB\rmO^2&\Leftrightarrow \left(\bun{r_1+r_2}{2}\right)^2=\left(\bun{r_2-r_1}{2}\right)^2+b^2 \end{aligned}$$と立式できるため,これを整理することで,
$$b=\sqrt{r_1r_2}$$が得られます。
面積の計算
以上から,$a=\bun{r_1+r_2}{2}$,$b=\sqrt{r_1r_2}$ であることがわかりましたので,楕円の面積は,
$$\pi ab=\Bun{\pi(r_1+r_2)\sqrt{r_1r_2}}{2}$$として求まります。
思いの外,大変ですよね。スムーズに計算できるように手を動かして練習しておきましょう!
.png)